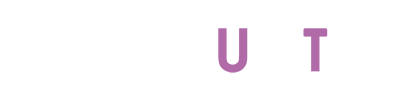ベースを買ってみたものの、何から始めたら良いか分からずに困っているという人も多いのではないでしょうか。
実際には複雑な知識は不要で、簡単なポイントを意識して練習を続けていけば、好きなアーティストの曲も弾きこなせるようになりますよ。

この記事のもくじ
ベース練習を始める前に
練習や演奏、音作りを快適に行うためには、ベースの基礎知識やセッティング方法などを知っておく必要があります。
特別なスキルや知識は不要なものばかりなので、実際にベースや機材に触れながら少しずつ覚えていきましょう。
まずはベース演奏に役立つ基礎知識を紹介するので、ベースを始めたばかりの人はぜひ参考にしてみてくださいね。
ライブUtaTenの関連記事!
-

-
ベース弦の選び方とは?初心者向けの種類やおすすめの弦7選を紹介!
続きを見る
ベースの役割を知ろう
練習を始める前に、バンド内でのベースの役割を知っておきましょう。
どんな役割があるかを知っておくと、練習の計画や目標が立てやすくなりますよ。
基本の役割はドラム共にリズムを支えることで、ギターやキーボード、ボーカルよりも低い音を使ってリズムのメリハリや流れを作り出しているのです。
また、ベースの弾く低音はコードの響きを決定付ける役割もあります。
地味なイメージがある弦楽器ですが、演奏次第でバンドのサウンドを良くすることができる奥が深いパートです。
アンプを設定しよう
エレキベースは、アンプのスピーカーを使って音を出す楽器です。
本体のみでも音は出せますが、実際にアンプから音を出したほうが演奏も楽しく、上達にもつながりますよ。
特に音色や弾く強さの確認に役立つので、右手の練習や弦を押さえる練習をするときにはアンプにつなぐようにしましょう。
ベースとアンプの基本的なつなぎ方や音作りのコツを紹介するので、アンプをセッティングするときの参考にしてみてくださいね。
つなぎ方
ベースをアンプにつなぐためには、シールドと呼ばれるケーブルを使います。
シールドをベース本体の差し込み口に挿し、反対側をアンプのインプット(INPUT)に挿すと接続完了です。
アンプに接続するときは、必ずアンプの電源がオフになっていることを確認しましょう。
オンになったまま接続してしまうと、アンプから大きなノイズが出てしまうだけでなく、アンプにも負担がかかってしまいます。
シールドを抜くときもオフにするのが基本なので「抜き差しをするときは電源を切る」と覚えておいてくださいね。
ツマミの調節
ベースをアンプに接続したら、いきなり練習を始めるのではなく、ツマミを調節して好みの音を作りましょう。
ベースアンプはギターアンプと同様に、音を調整するツマミによって音色を変えることができます。
スタジオに置かれているアンプには、細かな音の調整ができるグラフィックイコライザーが付いている場合もありますが、まずは基本のツマミの使い方を覚えるのがおすすめです。
- GAIN(ゲイン)
GAINはベースの音を歪ませたり、音量を足したりするためのツマミです。
最大まで回すと、ロックギターのようなジャリッとしたラウドな音になります。
他のツマミで音量や音色を作ったあとに設定するのが基本です。
- BASS(バス)
BASSは低音域を調整するためのツマミです。
目盛りの中央、時計でいうと12時のところを基準にして、音を聴きながら足したり引いたりしていきましょう。
強めにすると重厚な音になりますが、強すぎると抜けの悪いモコモコとした音になってしまいます。
- MIDDLE(ミドル)
ベースの音の中音域を設定するツマミがMIDDLEです。
音のハリや力強さをコントロールするツマミで、上手く設定してあげるとカッコいい音に仕上がりますよ。
BASS同様、12時を基本にして音を聴きながら調節しましょう。
- TREBLE(トレブル)
TREBLEは音のきらびやかさ、高音域の響きを調節するツマミです。
強めに設定すると固めの音、弱くすると丸い音になります。
音を装飾する役割が強いので、BASSとMIDDLEを設定した後に少しづつ足していく方法がおすすめです。
チューニングをしよう
チューニングは楽器の音を正しく調節することで、ベースを演奏する前に必ず必要となる作業です。
基本的に4弦をE(ミ)、3弦をA(ラ)、2弦をD(レ)、1弦をG(ソ)に合わせます。
音叉(おんさ)やメトロノームからAの音を出して合わせる方法もありますが、はじめはチューナーを使って正確に合わせるようにしましょう。
低い方から音程を上げながら合わせる方法が一般的で、高くなった場合は一度ゆるめてから合わせます。
こうすることで、弦がゆるみにくくなり、演奏中のチューニングの狂いを抑えられますよ。
全ての弦の音程を合わせたら、もう一度全体を確認しておくと安心です。
ドレミ(音階)を確認しよう
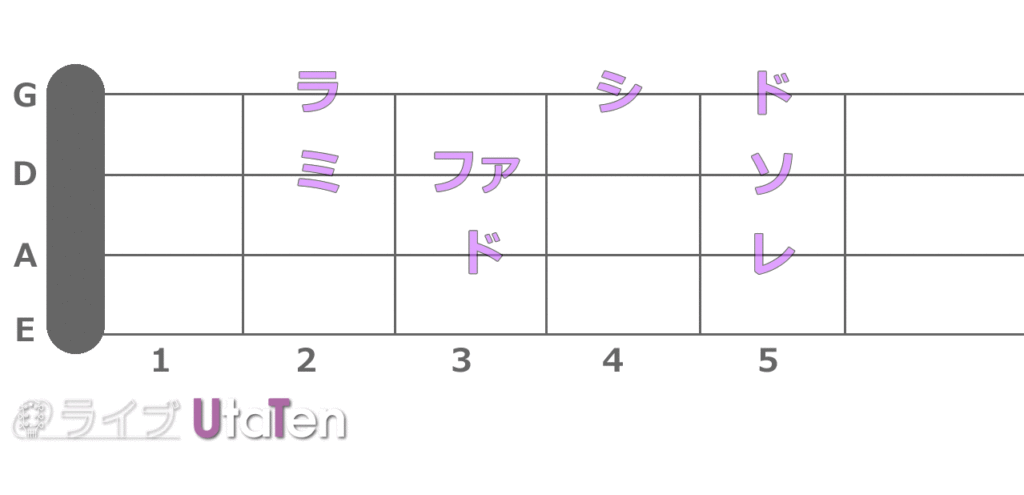
ベースの音階を確認しておくと、フレーズが理解しやすくなったり、応用やアレンジに役立ったりするので、少しずつ覚えていくようにしましょう。
指板上のドレミファソラシドは、上記の表のように並んでいます。
2フレット上の音は人差し指、3フレットは中指、4フレットは薬指、5フレットは小指で弾くのが基本です。
このドレミを覚えたら、ベース演奏でよく使う4弦1フレットのファ、4弦3フレットのソ、4弦5フレットのラ、3弦2フレットのシも足してみてくださいね。
あわせて、ドレミ音階と英語表記の「C(ド)D(レ)E(ミ)F(ファ)G(ソ)A(ラ)B(シ)C(ド)」と関連付けておくと曲を練習するときに役立ちますよ。
【ベース初心者】右手の基礎練習

ベース演奏において音色や音量、リズムをコントロールする役割を担当しているのが右手です。
右手を思い通りに動かせるようになると、シンプルなフレーズでもカッコよく聴かせられるようになりますよ。
定番の弾き方や右手のリズムを安定させる練習方法を紹介するので、ベース練習の参考にしてみてくださいね。
ライブUtaTenの関連記事!
-

-
ベースを始めるなら揃えたいものとは?必要な予算や一人で楽しむ方法を解説!
続きを見る
弾き方の選択
右手の弾き方には主に3つのスタイルがあり、それぞれに音の特徴があります。
演奏するジャンルや出したい音、好きなベーシストの弾き方を考えながら、どの弾き方が自分に合っているか考えてみましょう。
まずは3つのスタイルと基本的な弾き方、フォームを紹介するので、まずは自分にあった弾き方を見つけて練習してみてくださいね。
指弾き
指弾きは、右手の指を使った演奏スタイルです。
柔らかいサウンドが特徴で、音色の細かなコントロールができるため幅広いジャンルで使われています。
基本の弾き方は、弦の音を拾うピックアップに親指をのせ、人差し指と中指を使って弦をはじくツーフィンガー奏法です。
速いフレーズを弾く場合には薬指を足したスリーフィンガー、小指を足したフォーフィンガーも使われますよ。
ピック弾き
エレキギターと同様にピックを使い、ベースを演奏するスタイルがピック弾きです。
親指と人差し指でピックをはさみ、手首の動きを使いながら弦をはじきます。
ロックやメタル、パンク系のベーシストが好む弾き方で、音色もこれらのジャンルに合うリゴリとした固めの音が特徴です。
ピックの厚さや形、素材によっても音色が変わるので、色々な種類を試して、自分好みのピックを探してみましょう。
スラップ
スラップは親指で弦を叩くサムピング、人差し指を引っかけて弦を引っ張るように弾くプルを組み合わせた弾き方です。
バキッとした打楽器のようなサウンドが特徴で、ソロを弾くときやラウドな音を出したいとき、リズムを重視したフレーズを弾くときに使われます。
ベース奏法のなかでも特に目立つテクニックなので、バンド内で存在感を示したい人におすすめです。
裏クリックでリズム練習
裏クリックのリズム練習はメトロノームのテンポはそのままに、クリック音を裏拍に感じて練習する方法です。
リズムには裏と表という概念があり、メトロノームを普通に鳴らしたときに音が出る個所が表拍、鳴った音と次の音が鳴るまでの中間部分が裏拍になっています。
4拍子と8分音符を使って考えると、1、3、5、7個目が表拍、2と4、6、8個目が裏拍になりますよ。
拍を数えるカウントとメトロノームの音の関係が「1、ピッ、2、ピッ、3、ピッ、4、ピッ」となるように感じられたら裏クリックの成立です。
上手く感じられないときには、テンポを落としたり、手拍子だけで練習したりしてみましょう。
拍の感覚を鍛えるとリズムのキープ力が上がり、安定したベースラインが弾けるようになりますよ。
【ベース初心者】左手の基礎練習
ベースの演奏で、主に音程や音の長さをコントロールしているのが左手です。
また、音を揺らすビブラート、不要な音を鳴らないようにするミュートなども左手が担当しています。
右手と同様にポイントがいくつかあり、このポイントを押さえていくことで綺麗な音が出せるようになりますよ。
スタイルやジャンル問わず活用できる、左手の基本的な使い方や押さえ方、おすすめの基礎練習を紹介します。
弦の押さえ方
ベースのネックの握り方、弦の押さえ方には大きく分けて2つのスタイルがあります。
スタイルは押さえやすさに大きく影響するもので、手の大きさやジャンル、弾きたいフレーズなどによって使い分けられていますよ。
それぞれのスタイルの握り方やメリット、コツを紹介するので、どちらが自分に合っているか実際にベースを弾いて確認してみましょう。
クラシカルスタイル
クラシカルスタイルは親指をネックの中央部分、または中央より少し上の部分に置く弦の押さえ方です。
弦を押さえる指が動かしやすく、指を広げやすいのが特徴で、クラシックスタイルとも呼ばれていますよ。
手のひらをネックに付けないのがポイントで、親指とその他の指でネックをはさみこむイメージで弦を押さえます。
どんなフレーズにも柔軟に対応できるフォームなので、初心者や手が小さい人にもおすすめです。
ロックスタイル
親指を4弦に触れるくらいの位置に置き、ネックを握りしめるように持つのがロックスタイルです。
手の大きさによっては小指が使いにくくなる、指を広げるフレーズが弾けなくなるなどのデメリットがありますが、クラシカルスタイルよりも安定感がありますよ。
また、15フレット以上のボディに近いポジションでは、ロックスタイルの方が弾きやすいという人も多いです。
初心者にはクラシカルスタイルがおすすめですが、織り交ぜて使用することも可能なので、弾きやすさや手の形を考えながら色々と試してみましょう。
指の形
ネックの握り方を決めたら、次は力を入れやすい指の形を覚えましょう。
弦を押さえるときの指の形は2つの関節が曲がり、軽くアーチを描くのが基本です。
弦に当てるのは指先部分で、できるだけ指を立てて他の弦に当たらないようにします。
人差し指はヘッド側に向かって斜めになっていたり、他の弦に触れるくらいに寝ていたりしても大丈夫です。
爪が長すぎるとフォームが崩れやすくなってしまうので、ベースを弾くときには必ず切っておくようにしてくださいね。
弦を押さえる位置
弦を押さえる位置は、フレットの近くが基本です。
フレットの近くを押さえてあげると、最小限の力で綺麗な音が出せます。
真上を押さえてしまうと音が詰まりやすく、フレットから遠すぎると音程が悪くなったり、弦とフレットが当たるとビリビリとした金属音が鳴ってしまうので注意しましょう。
ベースの演奏に不慣れなうちは難しいかもしれませんが、できるだけ近くを押さえることを意識しながら練習すると簡単に押さえられるようになりますよ。
指の動かし方
弦を押さえたり、指を移動させたりするときには、最小限の動きで行うことを意識しましょう。
指を大きく動かしたり、効率の悪い動かし方をしてしまうと、指が疲れやすく、弦を押さえるときに無駄な力が入りやすくなります。
指を大きく動かす練習は指の力を鍛えることに役立ちますが、クセになると音も見栄えも悪くなってしまうので、演奏に慣れたら必要最小限の動かし方の練習もしてみてくださいね。
運指トレーニング
基本的な指使いやフォームを覚えたら、実際にベースを使ってクロマチック練習を行いましょう。
クロマチック練習とは、半音ずつ音を上昇、下降させるフレーズを弾く有名な運指練習用フレーズです。
4弦1フレットを人差し指で押さえて音を出し、次は4弦2フレットを中指、3フレットを薬指、4フレットを小指で押さえ計4回音を出したら3弦に移りましょう。
3弦から1弦までを同じ指使いで弾いたら、小指で1弦5フレットを押さえ下降パターンに入ります。
下降パターンは逆の指使いになっていて、小指、薬指、中指、人差し指の順に弾き、1つ上の弦に移動します。
このように上昇と下降で1フレットずつ指をずらしていき、人差し指が7~12フレットにくるまで続けてみてくださいね。
BPM60(1分間に60回程度拍数を刻む)ほどのゆっくりとしたテンポでフォームや音、右手と左手のタイミングを確認しながら弾いていくのがポイントです。
【慣れてきたら】ベース曲の練習

右手のピッキングや運指のトレーニングがある程度弾けるようになったら、実際に曲を弾いてベースの演奏を楽しんでいきましょう。
曲の練習はモチベーションの向上だけでなく、自分好みのフレーズや苦手な奏法などの発見にもつながりますよ。
ベース初心者にもおすすめの練習曲を、邦楽や洋楽、アニソン、ボカロなど幅広いジャンルから紹介している記事があるので、気になった人はぜひ読んでみてくださいね。
ライブUtaTenの関連記事!
-

-
ベースの練習曲おすすめ15選!初心者向けに洋楽からアニソンまで簡単な曲を幅広く紹介
続きを見る
ベースの基礎練習は地味だけど一番大切!楽しみながら無理なく続けよう
ベースの基礎練習はメトロノームを使ったり、クロマチックを弾いたりと地味なものが多いですが、実は演奏をするうえで一番大切なことが詰まっているのです。
リズム感や正しい運指は演奏力の土台となり、カッコいいベースラインを弾くための後押しをしてくれますよ。
焦ったり無理をせずに、楽しみながら少しずつ練習を続けてみましょう。
ある程度ベース演奏に慣れてきたら、教則動画やCD付きの教則本で理解を深めたり、好きな曲を弾いてみたりしてくださいね。
この記事のまとめ!
- 練習を始める前には、アンプの設定方法やチューニングなどの基礎知識を確認しておこう
- ベースの弾き方には指弾き、ピック弾き、スラップの3種類がある
- メトロノームを使った練習で、右手の動かし方やリズムを学ぼう
- 左手のフォームは弾きやすさに大きく影響するので、正しいフォームを意識しながら練習しよう
- 基礎練習に慣れてきたら好きな曲や弾きやすい曲を練習してみよう