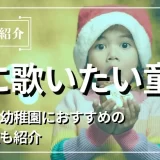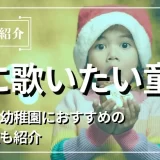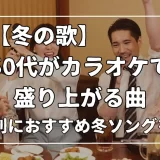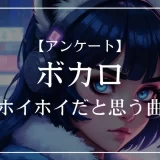1月はお正月など、年の始めならではの華やかさがあり、保育園でも特別な雰囲気がありますよね。
雪や北風など、冬の季節感も子どもたちにとって大切な想い出となります。
1月にぴったりな歌で、寒い冬もみんなで元気に遊びましょう。

この記事でわかること
1月の歌|保育園の乳児が楽しめる童謡
保育園の乳児には、身近な動物が登場する歌や、楽しい振り付けが目を引く歌が人気です。
1月ならもちつきや雪だるまなど、冬の活動をテーマにした歌がぴったりでしょう。
まず、保育園の乳児が楽しめる1月の童謡を紹介します。
コンコンクシャンのうた
風邪ひきさんの動物が多く登場し、それぞれが自分に合うマスクをつける「コンコンクシャンのうた」は、保育園の乳児と一緒に楽しめる冬の童謡です。
寒さが増して風邪をひく子どもが増える1月ですが、こんなかわいい歌を聞いたら、自分から進んでマスクをつけたがるかもしれません。
動物の特徴も出てくるので、動物の名前や形も覚えられます。
紙人形を見せたり、声色を変えて役作りをしたりなど、保育士さんのアイデアが活かせるでしょう。
もちつき
おもちの好きな子どもが関心を示す「もちつき」は、日本の伝統的な行事であるもちつきをテーマにした愉快な童謡です。
シンプルで短い曲なので、保育園の乳児が手遊びを交えて遊べます。
もちつきを見たことがある子はもちろん、見たことがない子でも「ぺったんこ」の音が面白くて、楽しく歌えるでしょう。
もちつきを知らない子のために、動画などでおもちができるところを見せると、イメージしやすいかもしれません。
雪だるまのチャチャチャ
寒い1月の保育園では、乳児と一緒に「雪だるまのチャチャチャ」を歌ったり手遊びしたりして、雪遊び気分を味わいましょう。
雪が降り雪だるまを作ったら踊りだしたという夢のある内容で、パパゴンだるま、ママゴンだるま、チビゴンだるまが登場します。
それぞれのキャラクターの特徴を分けて歌うと、面白いでしょう。
チャチャチャのリズムに合わせて、子どもたちに手拍子を入れてもらうと、さらに盛り上がります。
ぞうさんのぼうし
「ぞうさんのぼうし」は、ぞうさんが忘れていった大きな帽子から、いろいろな動物が現れるという楽しい歌。
ぞうさんを始め子猫や子豚など親しみのある動物が登場し、数が増えていくたびに変わる鳴き声に、子どもたちは興味をひかれます。
紙で作った大きな帽子から、動物の絵が飛び出すようにすると、次は何が出てくるかとみんなワクワクするでしょう。
繰り返しが多くて覚えやすい歌なので、乳児クラスにもおすすめの童謡です。
おもちをやいたとさ
子どもが大好きな動物が焼いたおもちがふくらんで、いろいろなパーツの形になるというユニークな童謡です。
おもちは伸びて伸びて、どんな形になるのか、子どもたちも興味を示すでしょう。
動物の特徴をアクションで見せるところがあるので、保育園の乳児も一緒になって手遊びを楽しめます。
「ぴょん」「ぱおーん」などのユニークな歌詞は、特に喜ばれるでしょう。
1月の歌|保育園の幼児が楽しめる童謡
保育園の幼児クラスになると、複雑なストーリーやキャラクターを理解して、より深く歌の意味を楽しめるようになります。
1月にぴったりな冬の歌で、イメージの世界を広げましょう。
続いては、保育園の幼児と楽しめる1月におすすめの童謡を紹介します。


北かぜこぞうのかんたろう
子ども向けの演歌として作られたと言われる「北かぜこぞうのかんたろう」は「ふゆでござんす」など時代劇風な歌詞がかえって新鮮な、レトロな雰囲気の冬の歌です。
1974年からたびたびNHKの歌番組「みんなのうた」で放送されてきた歌で、保育園の幼児の父兄にも親しまれているので、家で一緒に歌うかもしれません。
1月になり冷たい北風が吹く日を「北風小僧の寒太郎がやってきた日」とすると、寒い日も楽しみになるでしょう。
およげたいやきくん
「およげたいやきくん」は寒い冬になると食べたくなる甘い鯛焼きが、店から逃げ出して海を泳ぐというストーリー性の高い童謡です。
鯛焼きを売っているところでBGMとして使われることがあるので、聞いたことがある子もいるかもしれません。
1975年に幼児向け番組「ひらけ!ポンキッキ」でリリースされたヒット曲で、広い世代に親しまれてきた曲。
たいやきくんや背景を作って紙芝居のようにして歌うと、情景をイメージしながら楽しめるでしょう。
メトロポリタン美術館
「メトロポリタン美術館」はNHKの歌番組「みんなのうた」で放送され「ちょっと怖い歌」として話題になった曲。
夜の美術館(ミュージアム)の寒々とした雰囲気の中、天使の像やエジプトのファラオとタイムトラベルをする。不思議なストーリーを描いた童謡です。
子どもたちと一緒にイメージの世界を冒険しましょう。
冬の美術館や公園にある裸の像は大人から見るとアートでも、子どもの目から見ると寒そうで、靴下を貸してあげたくなるのかもしれません。
かぜもゆきもともだちだ
寒い季節、風や雪と遊ぶ子どもたちをテーマにした、元気いっぱいな冬の歌です。
外では遊べない日でも、保育園のお部屋で雪遊び気分を楽しみましょう。
クリスマスソングとされることもありますが、歌詞にクリスマスは入っていないので1月の歌としてもおすすめです。
オリジナルは「フロスティ・ザ・スノーマン(雪だるまのフロスティー)」というアメリカの歌に日本語の歌詞をつけたもので、古くから親しまれている冬の童謡です。
ゆきってながぐつ好きだって
雪が降る日に外を歩くと長靴や手袋に雪がついてくる、冬の独特な情景をユニークな擬音を交えて表現した、楽しい冬の童謡です。
雪が降ると保育園の通園は大変ですが、子どもたちは雪が大好きですよね。
そんな日に、この歌を歌えばますます盛り上がるでしょう。
キュキュキュやタタタタなど面白いフレーズが度々登場しますので、手遊びをしたり子どもたちを自由に踊らせたりして、元気に雪の日を再現してみましょう。
1月の歌|保育園で手遊びできる童謡
保育園で手遊びしながら1月の歌を歌うと、自然にお正月の楽しみや冬の習慣を学べます。
音楽や歌詞に合わせて手を動かすトレーニングにもなるので、積極的に取り入れてみましょう。
最後は保育園で手遊びできる1月の童謡を紹介します。


お正月
明治時代から歌われてきた、歴史あるお正月の童謡です。
男の子の遊びだった凧とコマ、女の子の遊びだったまりや羽つきが登場するので、手遊びをつけて楽しめます。
現代の保育園の子どもにとっては、馴染みの薄いおもちゃかもしれませんが、日本情緒のあるメロディに親しむ良い機会になるでしょう。
この歌を歌う前に、保育士さんからお正月の意味を説明したり、昔の子どもの遊びについてお話をしたりするのもいいでしょう。
今年もどうぞよろしくね
保育園で1月最初のクラスで歌いたい「今年もどうぞよろしくね」は、お正月の挨拶や意味を手遊びで学べるかわいい童謡です。
年の始めに笑顔で挨拶することを覚えましょう。
「あけましておめでとう」「今年もよろしくお願いします」は慣習的な挨拶ですが、意味がわかって言うのと、ただ言わされるのでは気分が違いますよね。
歌詞の始まりが「1」「2」「3」「4」の順になっているので、数字を覚えながら手遊びを楽しめます。
十二支のうた
「十二支のうた」は大人でも時々忘れることがある干支の動物たちを、楽しい手遊びで覚えられて、ためになる童謡です。
手拍子を交えながら十二支の動物たちや順番、十二支ができた言われについて学べます。
年末年始は「今年は◯年」「来年は◯年」などよく干支の話題が出るので、保育園でも十二支について理解を深めましょう。
どんな動物がいるのか理解しやすいように、動物の紙芝居などを使いながら歌うのもおすすめです。
雪のこぼうず
「雪のこぼうず」は雪をキャラクターに見立て、いろいろな場所に降る様子やその後の変化を表現した、かわいらしい手遊び歌です。
雪が降っても降らなくても、1月の保育園で寒い冬の空や雪が降る様子をイメージしながら、手遊びで場所や雪を表現してみましょう。
屋根や池、草地に降った雪のこぼうずはどんな運命をたどるのでしょうか。
「いーとーまきまき」で有名な世界的に親しまれている「糸巻きの歌」と同じメロディなので、覚えやすい童謡です。
にくまんあんまん
冬になると食べたくなる肉まんやあんまんなど、おいしそうな食べ物が次々と登場し、歌っているとおなかが空きそうな手遊び歌です。
フランス民謡が原曲の「グーチョキパーでなにつくろう」と同じメロディで、初めてでも取り組みやすいでしょう。
それぞれの食べ物にかわいいジェスチャーがあるので、保育園で1月に手遊びしながら歌うのにぴったりです。
徐々にスピードアップして、ゲームとして楽しんでもいいでしょう。
保育園児が楽しめる1月の歌をピックアップ!お正月の童謡で盛り上がろう
1月の保育園では、お正月やおもちなど新年らしい雰囲気の童謡や、北風や雪など冬の寒さをテーマにした歌で盛り上がりましょう。
乳児には、子どもが好きな動物が登場する歌、印象的な振り付けの童謡が人気です。
幼児になると曲の世界観やキャラクターを理解できるようになり、さらにイメージを膨らませるでしょう。
手遊びを通して、お正月や冬の雰囲気、挨拶などを学べます。
保育園児が楽しめる1月にぴったりな童謡を歌って、寒さを吹き飛ばすように元気に遊びましょう。
この記事のまとめ!
- 1月の保育園では正月や冬をテーマにした童謡や手遊び歌を歌おう
- 乳児は動物が登場する歌や手拍子などで参加できる歌が人気
- 幼児は歌のストーリーやキャラクターを理解して、より深く楽しめる
- 手遊び歌はゲーム感覚で正月や冬の習慣に親しめる
- 保育園で1月にぴったりな童謡を歌って盛り上がろう