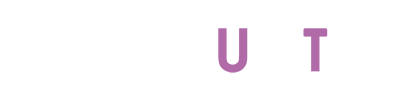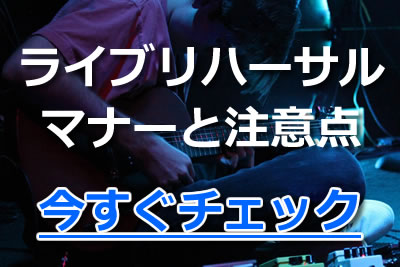ライブ前や音楽イベント前に行われるリハーサル。初めてのライブ出演だと、リハーサルで何をするのか分からないですよね。
「本番前に通しで曲の練習をするのかな?」と思っている人もいるかもしれませんが、音楽ライブのリハーサルには別の意味合いがあります。

ココがおすすめ
この記事の目次はこちら!
リハーサルをする意味って?
スタジオ練習に入って、いきなり演奏することはありませんよね。
スタジオでも楽器や機材のチェックをするように、ライブ本番でもチェックが必要になります。
ライブでは楽器や機材のチェックだけではなく、音量やお客さんからどう聞こえるかもチェックをするのです。

リハーサルで使う専門用語
音楽業界の共通言語が分からないとリハーサルで戸惑うので、リハーサルの際によく使われる7つの専門用語について説明します。
PA
PAとは「Public Address」の略で、直訳すると公衆伝達や大衆拡声という意味。バンドで鳴らした音を大きくして客席に伝えるための音響設備のことです。
その音響設備を用いて音の調節をしてくれるスタッフのことを「PAさん」「PAスタッフ」などと呼びます。
最高のライブを作り上げるには、PAさんはなくてはならない重要なスタッフです。
PAさんには礼儀正しく接し、積極的にコミュニケーションをとりながら「こういう音を出したい!」と要望を伝えるようにしましょう。
SE
「SE」とは「Sound Effect」の略。 自分たちのバンドが登場する時に使う音源のことをSEと呼びます。
「オープニングSE」などと言われることもありますが、簡単に言うと入場曲ことです。
SEをかけてもらいたい場合は、PAさんにあらかじめ曲をCD-Rで渡しておく必要があります。
また、SEを止めるタイミングや合図もPAさんに共有しなければならないので、メンバーであらかじめ話し合っておきましょう。
逆リハ・順リハ
「逆リハ」とは本番の出演順とは逆からリハーサルをしていくことです。
例えば4バンド出演する場合は「4→3→2→1」という順番でリハーサルをすることになります。
一方「順リハ」は本番と同じ順番でリハーサルすることを指します。
逆リハの場合、トップバッターのバンドでリハーサルを終えることになるため、セッティングをし直す必要がなく、一般的にライブでは逆リハが採用されていることが多いです。
しかし最近では、逆リハは各バンドの拘束時間が長くなることもあり、順リハを採用しているライブも増えてきているようです。
返し
演奏者が自分たちの音を聞くためにステージ上に置いてあるスピーカーを「モニタースピーカー」と呼び、そのスピーカーから出る音のことを「返し」と呼びます。
「モニタースピーカー」は「モニター」や「コロガシ」と呼ばれることもあります。
リハーサルの際にPAさんに対して「○○の返しを上げてください」などといった使い方をするので、覚えておきましょう。
3点
「3点」とは
- バスドラム
- スネアドラム
- ハイハットシンバル
の3つの楽器のこと。
ドラムには他にもたくさんのシンバルやタムがありますが、よく使われる3つのことを簡単に表すために3点と呼びます。
リハーサルで「3点ください!」などとPAさんから指示されることがありますが、これは「バスドラム、スネアドラム、ハイハットシンバルの音をください」という意味です。
ワンコーラス
曲の1番、つまりAメロからサビまでのことを「ワンコーラス」と呼びます。
リハーサルで全体の音をチェックする際は、ワンコーラスで演奏することが多いので、きちんと覚えておきましょう。
セトリ
「セトリ」とはセットリストの略。セトリはリハーサルではライブの曲順や照明の指示などを出演者が記入したリストのことを指します。
ライブハウスによって異なりますが、ライブではセトリをもとにPAさんが音響を調整したり、照明さんが照明の雰囲気を変えたりするので、必ず用意しましょう。
音量バランスの確認
ライブのリハーサルでは、音量バランスの確認をする必要があります。
ライブハウスとスタジオでは空間の広さが違うため、音の響き方が変わり音量調節が難しくなります。
慣れるまでは大音量になったり、逆に小さ過ぎて聞こえなかったりすることも。
大抵のライブハウスはスタジオより広いため、心持ちスタジオより大きめの音量で調整するといいでしょう。
万が一音量が小さすぎても、観客にきちんと聴こえるようにPAさんがバランス良く調整してくれるので安心してください。
ただし、大きすぎる場合はPAで下げることはできないので注意が必要です。
ステージ上で聞こえる音(中音)の調整
ステージ上には観客席ではなく、演奏する人のために内側に向いているスピーカーがいくつか用意されています。
先ほど「返し」の説明で出てきた「モニタースピーカー」です。
観客側に向いているメインスピーカーだけだと、ライブをする側では自分や他のパートの音が聞こえづらくなってしまいます。
そのため、スピーカーをステージの内側に向けて「中音(なかおと)」と呼ばれる演奏者のためのステージ上で聞こえる音を出すのです。
この中音のバランスが悪いと、演奏中に自分や他のパートの音が聞こえづらく、リズムを保つのが難しくなるので、リハーサルで中音の調整をする必要があります。
客席で聞こえる音(外音)の調整
「外音(そとおと)」とは、観客に向いているメインスピーカーから出る音のことを指します。
中音は演奏者にとって上手く演奏するために必要不可欠ですが、外音もお客さんに届ける音なのでかなり重要です。
外音は基本的にPAさんがバランスを調整してくれますが、ドラム以外の楽器メンバーは弾きながらステージから下りて、自分たちの音量バランス聞くことも可能です。
ボーカルの音量が小さいと感じれば、PAさんにお願いして自分の好みの音にしてもらいましょう。
ただしライブでお客さんが入ると、音の聞こえ方が変わることもあるので、初心者の場合はPAさんにお任せしておくのが無難です。
機材の確認
初めて出演するライブハウスであれば、リハーサルでそのライブハウスにある機材の種類や状態を確認しておく必要があります。
特にドラムはシンバルが割れていることや、バスドラムのペダルの故障などが発生していることもあるので、リハーサルの時点で確認しておきましょう。
リハーサルの時点で気付けば、ライブハウスのスタッフが本番までに対応してくれます。
また、キーボードなどの楽器を借りる場合は、自分が使っているものと使用方法が異なる場合もあるので、リハーサルで合わせて確認しておきましょう。
照明の確認
ライブパフォーマンスで照明のタイミングはかなり重要なので、リハーサルで必ず確認してください。
対バン形式のライブだと、照明さんが出演バンドの曲をすべて把握することは難しいため、曲のイメージに合わなかったり、照明のタイミングがずれてしまうことも…。
リハーサルで何曲か流れを聞いて、ある程度の照明を考えてくれますが、できるだけ多くの情報を照明さんに伝えておく必要があります。
当日演奏する曲順どおりに作った音源やセットリストをライブハウスに渡し、丁寧に説明しておきましょう。
セットリストに曲名ごとに「照明の雰囲気」や「色の希望」を書いておくと、照明さんが対応してくれます。
リハーサルの流れ

リハーサルの重要性が分かったところで、次はリハーサルの流れを知っておきましょう。
対バン形式のライブの場合、リハーサルは1バンド15分から長くて30分ほどです。

セッティング
リハーサルの順番が近付いてきたら、ステージですぐにセッティングできるように、エフェクターや楽器の準備をしましょう。
ライブハウスによってはスタッフから誘導される場合もありますが、指示が無い場合は必ず前のバンドが撤収したら自らステージに向かってください。
セッティング前には必ずギターやベース、ドラムのスネアなどのチューニングは忘れずに。
ギターやベースはエフェクターの配線もステージ上を想定して繋いでおきましょう。
セッティングが無事完了したら、メンバー全員が準備できたことを確認して、PAさんに「セッティングOK」ですと伝えるのがマナーです。
各楽器のサウンドチェック
セッティングが完了し、各楽器のサウンドチェックが始まったら、PAさんの指示をしっかり聞きましょう。
基本的には
- ドラム
- ベース
- ギター
- ボーカル
の順番にサウンドチェックを行います。

ドラムのサウンドチェック
ドラムは「キックください」とPAさんから指示がありますが、これはバスドラムのことなので、本番の演奏と同じ音量になるように「ドッドッ」と踏みましょう。
その後、スネア、ハイハット、ハイタム、ロータムをPAさんからの指示通り叩きます。
「全体ください」と言われたら、基本的な8ビートをいつも通りのスタイルで叩けば大丈夫です。
ベースのサウンドチェック
ベースは「ベース音ください」などと言われるので、演奏で使う一番低い音から一番高い音を適当に弾いたり、演奏する曲のフレーズを弾いてください。
指弾き・スラップなど音の変わる奏法がある場合は、PAさんに伝えてから弾くといいでしょう。
ギターのサウンドチェク
ギターもベースと同じく「ギター音下さい」と指示があるので、エフェクターで使う音色ごとにワンフレーズ弾いていきます。
ボーカルのサウンドチェック
最後にボーカルですが、恥ずかしがらずに挑むのがコツです。バンドの顔であるボーカルなら実際に歌う音量でワンフレーズ歌ってみましょう。
フェスなどでよく見るサウンドチェックで「ヘイ!」「1・2チェック」をしなければいけないと思いがちですが、その必要はありません。

PAさんが音のバランスを調整してくれるので、必ず指示があるまでは音を出し続けるようにしましょう。
全体の音出し
各パートの音出しが終わると、PAさんより全体の音出しの指示があり、「外音」「中音」「全体」の音量の調整を行っていきます。
まずは全体的に音量が大きい曲を演奏してバランスをとるのがおすすめ。あらかじめメンバーと何の曲をリハーサルで演奏するか話合っておくといいでしょう。
リハーサルはあくまで音量バランスの調整を行うためにあるので、全体の音出しでは1曲丸ごと演奏する必要はありません。曲の1番やサビだけを演奏するようにしましょう。
演奏し終わったら、中音の調節をPAさんにお願いし「ボーカルが聞こえづらい」「ギターが大きすぎる」など気づいたこと修正しましょう。
モニターの返しにはそれぞれ好みがありますが、基本的にはドラムやベースのリズム音を大きく返してもらうと、演奏を合わせやすいのでおすすめです。
もし、聞こえづらいパートがある場合はPAさんに「○○の返しをもっとください」などと伝えましょう。
曲のリハーサル
リハーサルで時間が余れば、残りの時間で曲のリハーサルができることも。練習ではなく本番にむけての最終確認という意識を持って曲を演奏することが大切。
必ずメンバーで「この曲のサビまで」「この曲のBメロから間奏まで」など、演奏する曲とその部分を決めておくことが大切です。
もし演奏途中で中音に聞こえづらさや違和感を感じたら、PAさんに返しの調節をお願いしましょう。
PAさんに要望を全て伝え終わったら、リハーサルは終了。リハーサルの演奏も初めは緊張しますが、落ち着いて音を聞くことに集中しましょう。
セッティングをメモ
リハーサルで準備したことを再現すると、同じ状態で本番を迎えられます。
ギター・ベース・キーボードは、リハーサルでの音出しや演奏が終わったら、必ずアンプの目盛などのセッティングをメモしておき、スマホが手元にあるなら写真で撮るのもおすすめ。
「すぐに片付けないと」と焦って忘れそうになりますが、本番でセッティングが変わったらリハーサルの意味がなくなります。
メモを取ったら素早く片付け、次のバンドリハーサルや本番の時間に配慮しましょう。
リハーサルでのマナーや注意点
初めてのライブだと戸惑うことが多い「リハーサル」ですが、良いライブをするためには必ず守るべきマナーがあります。
ライブは出演者とスタッフが一緒に作り上げるものなので、マナーや注意点は抑えておきましょう。
良いライブにするためにも、リハーサルでの5つのマナーと注意点をチェックしてください。
ケーブルを踏んだりシールドを急に抜いたりしない
ステージ上には無数のケーブルが敷かれています。ケーブルは意外と簡単に断線してしまうので、踏まないように足元には気をつけること。
また、アンプの電源が入っている状態や音量が0になっていない状態で、シールドをいきなり抜くとアンプの故障に繋がります。
PAさんに「シールド抜きます」と声をかけてから抜くようにしましょう。
スケジュールを押さない
メンバーが全員揃わないとリハーサルは始めることはできません。遅刻は絶対しないように心掛けましょう。
また、リハーサルの時間も押さないように、時間内で終わらせます。前後のバンドのリハーサル時間やライブの開演時間にも影響します。
リハーサルの際に自分のセッティングが終わって余裕があるなら、他のメンバーのセッティングを手伝いに行くなど、打ち合わせしておくといいでしょう。
他の楽器の音量調整中は音を出さない
自分以外のメンバーがサウンドチェックをしているときに、音を出すことは絶対に避けてください。
PAさんもメンバーも音が聞きづらくなり、リハーサルの進行を妨げてしまいます。
パートごとの音量を調整するための大切な時間ということを忘れないようにしましょう。
しっかりと挨拶やお礼を言う
ライブハウスのスタッフはもちろん、共演者・PAさん・照明さんには必ず挨拶をしましょう。
リハーサルのときもPAさんに「よろしくお願いします」「ありがとうございました」など、言葉をかけることが大切です。
また、自分のバンドの出番が終わった時に「お疲れ様でした」と言われたら嬉しいですよね。他の出演者の出番が終わった後も挨拶を心掛けましょう。
ライブハウスでは自分が思うより、大きな声で言わなければでは聞こえないので、元気よく笑顔で挨拶とお礼は伝えるといいでしょう。
中音を優先的に調整する
中音は本番中に変更することができないので、リハーサルで一番優先的に調整する必要があります。
もしライブ中に中音を変更したくても、お客さんがいる中PAさんに向かって「モニター上げてもらっていいですか?」なんて言えません。
外音も大事ですがPAさんが調整してくれるので、リハーサルではなるべく中音に集中しましょう。
リハーサルの目的はズバリ音の調整!裏方さんと一緒にベストな状態を作り本番につなげよう!
実際にリハーサルをしてから「初めて分かること」がたくさんあります。
スタジオとは違って音が聞こえづらかったり、照明が暗くてエフェクターや機材が見えづらかったり、いつもと違う状況での演奏に戸惑うこともあるでしょう。
しかし、リハーサルは本番で最高のライブを披露するために、音の調整をする大切な時間です。
しっかり集中してリハーサルを終えたら、あとは本番で思いっきり演奏を楽しむだけ!リハーサルでベストな状態を作って本番を迎えましょう!
この記事のまとめ!
- リハーサルでは中音や外音のバランス調整を行う
- セッティングを速やかに行い各パートのサウンドチェックはPAさんの指示に従う
- リハーサル用語を覚えておくとPAさんとのやり取りがスムーズにできる
- ケーブルは踏まないように要注意!シールドは勝手に抜かずPAさんに確認しよう
- PAさんや他のバンドに対するに挨拶とお礼を忘れずに
- ライブでは中音が重要!優先的に調整してライブ本番に備えよう