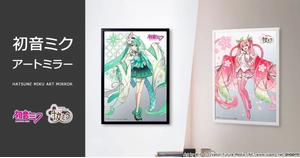紆余曲折、全部この街で経験してきた
──2021年に開催された初のアリーナツアー『都会のラクダSP ~愛の大砲、二夜連続~』のファイナル公演で、ニューアルバム発売とタイトルが発表されました。タイトルの『東京』がバーンとスクリーンに映った時、「うわ!」と思って。すごい迫力を感じたんですよね。
渋谷龍太:ビジュアルが強いですよね(笑)。
──はい、漢字二文字のタイトルはインパクトがありました(笑)。そしていろいろ想像させる名前ですが、なぜ『東京』というタイトルを掲げようと思われたのでしょうか?
渋谷龍太:タイトルは最後に決まったんですよね。曲がある程度出そろって、レコーディングももう折り返しを過ぎていた時に、“アリーナの最終日で発表するから、アルバムタイトルを決めておかないとね”となって。タイトル未定でもいいんだけれど、決まっていた方がやっぱりインパクトがあるから、ここでもう照準をしぼらなきゃいけないな、と。
この『東京』というタイトルは、『東京』という楽曲が入っているアルバム以外に、今後たぶんつけられないであろうタイトルですよね。さらに『東京』という曲は、誰もが自分が育った場所を思い起こせるというか、聴いてくださる方の気持ちを入れることができる器の大きさがある楽曲なので、アルバムタイトルにすることによって、聴いてくださる方に寄り添えるな、と考えました。
これを掲げられるのは、バンド人生一回の必殺技だと思っているし。メジャー再契約をしてから2枚目のアルバムで、ほぼセルフタイトルと言ってもいいぐらいのタイトルを掲げられるのは、自分たちとってすごく良いことだと感じたので、メンバーも満場一致で『東京』にしようと決まりました。
──「東京」はSUPER BEAVERにとって、セルフタイトルなんですね。
渋谷龍太:だと、思いました。僕らが生まれて育ってきた町はやっぱり東京で、酸いも甘いも、紆余曲折、山あり谷ありは、全部この街で経験してきたので。他のバンドが掲げる東京とは、また少し意味合いが違う。ただその場所の歌を歌っているわけではない、というのは僕らしかできないかな、と思っています。
──タイトルを見てから、どんなアルバムが来るのかワクワクしていて、完成した作品を聴いたら、本当に想像を超えたバラエティ豊かな一枚だと感じました。まず前半ですが、前作のアルバム『アイラヴユー』(2021年2月リリース)は『今夜だけ』という葛藤を抱えた曲で始まっていましたが、今回は1曲目の『スペシャル』からトップスピードで突き進みますね。
柳沢亮太:今回は、“どういうアルバムにしようか”ということ以前に、藤原と上杉が“サウンド面やアレンジで、ライブやライブハウスの香りがするアルバムがいいよね”と言っていて。2020年の『アイラヴユー』は、ライブはなかなかできなくて、良くも悪くも制作期間もたっぷりあった中で制作したアルバムだったと思うんです。
でも2021年はコロナ禍でもライブ活動ができていたので、それこそアリーナもそうですけど、ホールもやりましたし、ライブハウスも同時にグルグル回っていたので、今一度ライブハウスだったり、ライブ会場の空気感だったりみたいなものをサウンドとしてもパッケージングできたらいいよね、という話をしていました。
──上杉さんと藤原さんがライブハウス感をアルバムの芯として入れたい、と思ったのは、どういったことがきっかけだったのでしょう?
上杉研太:2021年に数多くのライブができたことと、繋がっていますね。僕らは現場至上主義といって、ライブというものにフォーカスを当て続けて活動しているバンドです。だからアリーナなどに立てるようになった状態の今、もう一度、どこでやろうがライブハウスが見えてくるような、そこで鳴っているような感覚にフォーカスを当てたい、という気持ちになって。2021年のバンドの勢いを感じる、バンドのスタンスがすっと出ているような雰囲気のアルバムになっている気がしますね。
藤原”33才”広明:“今、どういう音楽を聴きたいんだろう? 喜んでもらえるんだろう?”と考えた時に、ライブっぽいもの、というのを単純に思ったんですよね。コロナ禍で家にいるから外に出れないとか、ライブに行けないという状況の時に、たとえ家にいても、ライブの楽しい感じやリアルさが思い出せたり、想像できたりするアルバムになったらいいなというのは、最初に漠然と思って。
それでリーダーと“どういうのがいいかな”と話している時に、“ライブっぽいのがいいんじゃないか?”ということを言ったんです。テンションが高いというか、元気というか。そういう印象のものになった方が、喜んでもらえるんじゃないかな、と漠然と思った記憶があります。
MCで出た「人間冥利」がキーワードに
──前作のアルバムは、どちらかというとマクロ的な視点というか、全体を俯瞰して包み込んでいる感じがあったのですが、今回の『東京』は生々しさというか、個別にフォーカスしているような曲が多いと思ったんです。そして1曲目の『スペシャル』と2曲目の『人間』がスタート部分にくることによって、“あなたが主役”というか、アルバムの中に聴き手をポン、と立たせている印象を持ちました。
柳沢亮太:今回は“こういうコンセプトで作りましょう”と大きくスローガンを掲げたわけではなかったんですけれど、『スペシャル』でも出てくる“人間冥利”というワードが、渋谷のMCで出てきて。これは今作のキーワードの1つになり得るな、と思ったんです。
これまで“音楽家冥利に尽きる”とか“バンドマン冥利につきる”ということをステージで口にしていたのは聞いていたのですが、ある日突然、“もっというと、人間冥利に尽きるなあ”と言っていて。人間冥利って普段はあまり聞かない言葉ですけれど、それが“今、歌いたいな”と何となく思っていたこととすごくマッチして。“人間冥利って何だろう?”と自分なりに考えたのが、まさにおっしゃってくださった、生々しいと言うか、人くさいな、ということで。
それは『人間』という曲にも通じるんですけど、“全部が全部好きなのかと聞かれると、まるっきり好きとは言い切れない。でも嫌いとも言い切れない”みたいな。“分かるし、分かんないよ、その気持ち”みたいな部分も、今一度ちゃんと歌にしていきたいと思ったんです。それでメンバーにも“人間冥利というのは、1つ軸にできるんじゃないか”と話して。
ことさら自分もすごく感じたのは、おっしゃってくださったように『アイラヴユー』とあえて比較するのであれば、前作はわりと4人から発せられるメッセージなんですけれど、今回の『東京』というアルバムは、本当に聴いてくださる方一人ひとりによって、響き方とか、響かせ方が違うんだろうな、と思いますし、そうだったらいいなと、これまで以上に思います。
──MCで“人間冥利”という言葉が出てきたのは、何がきっかけだったのでしょうか?
渋谷龍太:MCは発作的に出るものが多くて、ほとんど覚えていないので…(笑)。ただやっぱり、2020年のフロアに見に来てくださる人がいない状況を経て、2021年に定められたルールの中で、お客さんを入れてライブをやろうと決断した自分たちがいて。その意志に賛同して見に来てくださってくれる方がたくさんいて、ルールをしっかり守り、誰一人暴走することなく、しっかり見てくださっていた。
その状況を見て、“見に来てくださる方と一緒に作り上げるから、ライブができる”と認識したんです。この状況を作って賛同してもらって、結果、一緒に作り上げられているのは、バンドマン冥利に尽きることだとつくづく思ったところから始まって。“音楽家冥利につきる”、つまるところ自分たちにとって、それは人生とイコールみたいなものだから、“人間冥利につきますね”とぱっと言ったのは、なんとなく覚えてますね。
──そして映画「東京リベンジャーズ」の主題歌でもある『名前を呼ぶよ』が続き、4曲目に『ふらり』という軽快なナンバーが来ます。
柳沢亮太:これは単純に“ロックンロール的というか、軽やかな楽曲がアルバムにあったら、ライブは楽しいよね”という話からできました。だから曲の空気としては狙いながら作ったんですけど、歌っている内容としては、いろいろな具体的な瞬間というか、シチュエーションみたいな部分が今作はすごく歌えたかなと思っています。
何か人間的であるというところのひとつに、経年による変化があると感じていて。自分たちもバンドを始めて17年目で、年齢を重ねたからこそ感じられたこと、重ねても変わらないものと、いろいろあります。一本芯を通すというのも、すごく素敵なことだと思っていますけれど、その筋の通し方というのは、やはり10年前と今とでは変わってくる。でもそれはシンプルに素敵なことだというのを、歌にできたらいいなと思ったのがこの楽曲なんです。
──経年による変化って、いい言葉ですよね。
柳沢亮太:まさにこの歌詞で書きたかったんですけど、なりふりを少し構うと言うか、自分の見方みたいなものを考えるのって、間違いなくその周りに大切な人がいるからだと思うんですよね。たった自分一人で奮闘するのであれば、どんな風貌で、どんな表情で、必死なだけであっても別に構わないと思うんですけれど、自分の存在を客観的に見たいと思える理由って、やはりそばに人がいるからなんじゃないか、と個人的に思っていて。
年齢を重ねれば重ねるほど、それぐらい思いたい人というのは増えてきていて。それが自分たちのエネルギーになっているのは間違いないと思います。それが“大人って楽しいな”と思う一つの理由ですし、そういったところは、年々すごくいいな、と思っています。
──曲調は、本当に軽やかで楽しくなります。
渋谷龍太:曲に呼ばれた歌だとは思っています。こういう歌がこの歳になって歌えているのはいいことなんじゃないですかね。そうじゃないパターンもあったと思うし。
──そうじゃないパターンと言うのは?
渋谷龍太:今、生き方の差が露骨に出てくる年だな、と思っていて。僕は同世代、年下の世代、上の世代と均等に会うようにしているんですけれど、この年齢あたりが分岐点で。どんな生き方をしてきたかとか、今、どんなこと考えて、どういうふうに生きようと思っているのかが露骨に出るので、一番油断しちゃいけない年齢だな、と思って。だからこういう年代でこれを違和感なく歌えることが、非常に大事なことだと考えています。
後は楽しい曲調でライトな曲だとは思っているのですが、責任感もすごくある曲だなと。これをかっこよくない生き方をしていて歌ったら、また響くものがまったく違うと思うんですよ。今まで自分はこの曲に意思を持たせるとか、説得力を持たせる生き方をしてきたつもりだし、ちゃんと響かせられるな、と思っているんですけれど、発信したからには、この後もそういう生き方を続ける覚悟を持たないといけない。その責任は持たなくてはいけないと、いろいろ考えました。
“この人が言っているのだったら、そうでしょう”とならないと、聴いてくれた人が“じゃあ、自分も”と心を許したり、肩の荷が少し降りたりする感覚というのは作り出すことはできないと思うので。
──聴き手としてはすごく陽気になれるんですけれど、伝える側にはそういった覚悟が必要だと。
渋谷龍太:口当たりは“楽しい曲”でまったく問題ないんですけれど、そういうものを作るには、楽天的なところだけでは内容が伴わないというか。たとえばおもちゃを作っている人は、“こういうことで、こうなったら”といろいろ考えた上で、子どもが遊ぶものを生み出しているわけで。何も考えない、おもちゃのような人間が作っているわけじゃないんですよね。作り手はそういう責任の一端を担うべきだと思っているので、一旦、自分の中に全部落とし込んで解釈し、そのうえでふわっとさせる。それが大事な作業ですね。
──考え抜いて、考え抜いて、でも作品に表す時は、その苦労を見せない。あくまでも作品としてかっこいいか、なのですね。演奏面では、どのような点にこだわりましたか?

藤原”33才”広明:この曲は最初アレンジをする時に、自分の同級生とか、それこそ同世代の友人とでも普通にサラリーマンやってるやつとか、結婚して子どもがいる人とか、ふらっとライブに来て、楽しんでもらえるような感じになったらいいかな、と。
『ふらり』というタイトルは後からついたんですけど、何か軽やかな感じで。ライブ来た時は、久々に楽しめるようなほっこり感というか、日常に帰った時に元気になれるようなものになればいいかな、と。だからこうしようと考えてやったというよりは、それくらい受け止めやすいものというか、ノリやすいというか、楽しみやすいものになればいいなと思っていました。
上杉研太:めずらしく、いろいろな場面転換もあって。1つのストーリーの中で、さまざまな面白い場面が作れたらいいな、とは思いました。
現場のドキドキ感をパッケージした
──6曲目に来る『VS.』は、まさにロックバンドの真髄!というか、せめぎ合っている感じが、ひたすら熱くてしびれました。
上杉研太:この曲は制作でいろいろつめている段階からどんどん盛り上がっていって、もともとあったアレンジからガラッと変わったりしたんです。そうやってみんながワクワクしながら作っていて、“これは先に録っちゃおうか”となって、この曲だけ圧倒的に早いスパンで録ったんです。作っている時の“うわ、かっこいい!”といった空気感が、そのままパッケージされてる曲になりましたね。
藤原”33才”広明:急に“録ろう”となって、“マジか?”と思いました(笑)。どの曲でもなんですけれど、一応、自分の中では“こういう感じと、こういう感じ”とアイデアを複数持って行くんですけれど、当初はメインでは考えていなかった案に対して、“それも面白いね”となって、そういったことがきっかけで、がらっとアレンジを変えて、その場の勢いで方向性をガーっと変えていって曲ができたんです。
だからそれを“すぐパッケージしたい”となって。エンジニアもノリノリでした。そういう現場の空気をそのままパッケージした方が面白いというか、聴いてもらう人にもドキドキ感みたいなものが伝わるチャンスなので、ちょっと大変だけれどやろう、となったんです。でも思った以上に強くできました。それもチームで長くやってきたから、“こっちだ”と方向が決まったら、すぐみんなでいいものを作れるという空気がすごくあって。楽しみながら作ることができたと思います。
──ちなみに『VS.』で描こうと思われたテーマは?
柳沢亮太:歌詞はもうちょっと分かりやすい物語にしたいと思ったんですけど、その時まだ歌詞ができあがりきっていなくて。他に『それっぽいふたり』とかもあって、絶妙な距離の機微を歌えた楽曲が収録できるとなった時に、どうしようかなって思いながら音を録っている時に、“純粋にかっこいいから、このままいっちゃおう”となって。
だからいつも以上に具体性をあえてなくして、心の本能的なところが勝つのか、理性的なところが勝つのか、というせめぎあいをずっと描いていく楽曲にしようということに行き着きました。多分過去一番ぐらい、何の答えも出ない曲というか、せめぎ合ったままというか。バンドサウンドも、各楽器がせめぎ合っているので、人間くさいとか人間冥利というところとはまた別の角度から、こういう楽曲があるというのはいいな、ということで、この形で最後まで行きましたね。
──この曲は特にライブでどんな爆発力を見せてくれるのか、楽しみで仕方ありません。
柳沢亮太:今までのSUPER BEAVERには、こういうふうに振り切った曲はなかったので、ライブをやる中でどうなっていくのかは分からないですけれど、今までにはなかったステージをまた一つ出せる曲になっているんじゃないかな、と思います。
──ひたすら音に身を委ねたいと思いました。
渋谷龍太:これはほぼ、歌も楽器ですよね。なので、歌を真ん中に置いてどう展開するかというよりも、4人で展開していくイメージがあったので、自分は先頭を切っている感じはしなかったですね。
──まさに渋谷さんのボーカルも楽器の音とひとかたまりになっていますよね。続く『それっぽいふたり』は、身に覚えのあるような、ないような、不思議なリアル感があります。
柳沢亮太:この曲はちょっと前からあった曲で、このアルバムを作ろうとなって作り始めた楽曲ではなかったんですけれど、逆に人間冥利というキーワードなどが出てきてから、“こういう楽曲がこのアルバムに入ってきたら、またさらに視点が増えるな”って思って入れました。これはまさにそれっぽい感じの、“どこかに覚えがあるような、ないようなこの関係”みたいなものを、すごくリアルに描写できたのかなと思っていて。僕もこの歌詞がすごく好きで。自分で書いておいてなんですけど、何か“分かるな”と思う感じがあるんです。
この曲の2人は、すごくいい感じっぽくて、実は何もないんじゃないか。何もない感じすら、ちょっとしゃれているんじゃないか、とか。そういったものが、曲として形になったな、と思います。
──8曲目の『318』は、色っぽいけれど、どこか無機質な感じもある、沼に入っていくような楽曲だと思いました。
渋谷龍太:この曲は、柳沢に色味をオーダーして作ってもらったんです。そもそもはまったく違う曲だったんですけれど、“紫っぽい曲がほしい”と言っていて。SUPER BEAVERって赤とか黄色とか水色とかが多いと思うんですけれど、紫色の曲ってあまりないな、と思っていて。それで最初に作ってもらったのが、実は『VS.』だったんです。それで“ちょっと違う”と感じて、柳沢も“それを目指して作ったんだけれど、ちょっと違うかも”となって。
柳沢亮太:そうだったね。
渋谷龍太:でも“これはかっこいいから、このままやろう”となり、結果的に紫っぽい曲がなくて。柳沢が“元にあった曲をちょっと変えてみた”と、この『318』の原型を作ってくれて、“すごくいい感じだね”となったんです。でもその時は、歌詞がこういう感じではなかったから、ちょっとチグハグさがあって。できるなら、そっち路線で書き換えて欲しいと頼んで、柳沢に書き変えてもらいました。
その結果、こういう曲になったので、わりと異質でよくて。SUPER BEAVERの今までのアルバムにはなくて、ライブで展開していく上で、“こういう曲が1曲あったら、すごく良いな”と思っていました。リズムも今までにない感じですね。ツアーをやって1時間半、ないしは2時間近くライブをやってる中では、ある程度の緩急はどうしても必要です。真面目な曲をぐっと真ん中にストレートを打ち込むにも、ずっとストレートっぽい曲では免疫がついちゃうし、伝えたいことの本質がぼやける可能性も出てくると思っていて。なので、ある程度、回り道したりとか、右からいったり左からいったり、下からいったり。人間としてもそっちの方が面白いじゃないですか。
──確かに、そういう人の方が気になります。
渋谷龍太:真面目な話もできるけど、ふざけられるやつの方が面白いし。ただ、ふざけてるだけのやつは面白くなくて、真面目な気持ちもある方が興味を持てる。そういうのをアルバムでもライブでも表現できたらより人間的だし、いろいろなところに作用するかな、と思うんです。この曲だけではなくて、ライブ一本を通してこういう曲があったらいいな、というのはすごく思っていたので、いい役を担っているんじゃないでしょうか。
──ちなみに『318』のタイトルは環状七号線からだそうですが、それも具体性があって、『東京』というタイトルにつながっていますね。
柳沢亮太:そうですね。ちょうどこのレコーディングの前後くらいで、レコーディングスタジオに行くのに環七も通ったりしました。
これはあくまでイメージなんですけど、なんとなく夜っぽい空気というのは、最初から脳内で感じていて。何か大人っていうより、ちょっとアダルトというか、そういった空気をまとえたらいいな、と思いながら作っていました。
──渋谷さんの艶っぽいボーカルがこの曲の世界を彩り、柳沢さんのギターが心をかき乱し、上杉さんのベースがそっと寄り添い、藤原さんのドラムが迫ってくるという、本当に濃厚なナンバーで。このアルバムを経て、SUPER BEAVERのライブが、またひときわパワーアップしていくことを確信しました。上杉さんはこの曲について、いかがでしたか?
上杉研太:それこそ経年変化を感じるような曲というか。この30代を超えてきて、ちょっとずつ年を重ねたからこその空気感がある気がします。でもリズム的には、ジャズっぽいというか。この年齢になって、ステージで映えるようなところがあるのではなかろうかというアプローチになっていて。まさに紫っぽいというかね。だからこれまた新たなSUPER BEAVERだし、ライブで映える楽曲ができたんじゃないかな、と思います。
皆の元に届いた瞬間に完成する一枚
──後半の9曲目『未来の話をしよう』からラストの『最前線』までは、SUPER BEAVERらしいというか、1つの線になってたたみかけてきます。柳沢亮太:このアルバムの中で、「ロマン」という曲が最後にできたので。ただ「東京」は、やっぱり後半のこのあたりに置きたいねと言いながら、曲順もわりと最後の方までパズルのように置き換えていたんです。結果として「未来の話をしよう」から「最前線」の流れというのは怒涛だな、というのは分かりながら組んだ曲順でありました。
『未来の話をしよう』は、今作に絶対入れたいなと思った曲で。『アイラヴユー』の時は、否が応でも2020年から始まったことを意識せざるを得なかったというか、意識しないようにしようということすらも、意識として入っているというか。そういうものも含まれたアルバムだと思うんです。
でもそういうのを抜きにして、今この楽曲を届けることができたら、自分の歌として聴いてくれる人が多いんじゃないかな、と何となく思っていた曲で。『突破口』という曲で「今をやめない」と歌っていたバンドが、その次に「未来の話をしよう」といえる、この絶妙な感じが、すごく今のSUPER BEAVERっぽいな、と思えた曲でした。
──アルバムの要でもある10曲目の『東京』に関してはいかがでしょうか?
渋谷龍太:やっぱりこのアルバムの土壌を作っている曲だな、という感じがすごくしますし、器がでかいからこそ、他の曲を入れられたんだな、という立ち位置の曲だと思っています。実は『アイラヴユー』の時からあったんですけれど、今でよかったなと。もちろん『アイラヴユー』の時に出してもちゃんと響いた曲だとは思うんですが、2020年と『アイラヴユー』を持って回った2021年があったからこその感覚みたいなものを、ここに落とし込めたと思うから。入るべくして、このタイミングで入ったんだろうな、という感覚はありますね。
──そしてラスト、これぞフィナーレといった多幸感にあふれた『最前線』が来ます。
藤原”33才”広明:最初から結構、この曲は最後がいいな、と言っていて。最後にみんなで「行け 行け 行け」ってみんなで歌っている感じが、すごく良くない?という会話は最初からずっとしていて。
そのイメージが最初にあったから、並べ方とかすごく決めやすかったですね。デモを作る時は、“1曲目とかで、あまり展開しないで、さらっと入れるような曲があってもいいよね”という会話をしてワイワイ作った中で完成した1曲だったと思うんです。それが最後にちゃんとはまったのは、面白いなと思いました。
──「行け 行け 行け」って、まさしく背中を押す歌詞ですよね。拳を上げて、今は心の声でですが、熱く叫びたくなります。
藤原”33才”広明:コロナ禍でいろいろあって、ライブに行くのも行かないのも、それぞれ個人の判断ですべて正しいと思うんですけれど。ただ、このアルバムを聴いて、この終わり方を体感すると、“ライブに行こうかな”という気持ちになる曲順になったと思います。
──このアルバムが完成した今、どんな手応えを感じていますか?
上杉研太:紛れもなく、すごくいいものができていて、SUPER BEAVERの新しさとか、いろいろなチャレンジが入っているんですけれど、この作品は今まで以上に聴いてくださる方に届いてから、形になる気がしていて。前作の『アイラヴユー』という作品はすばらしくて、できた瞬間に、“これは最高だ! 最強だ!”と思って同じような感覚ではあったんですけれど、何か今回はまだ最後のピースが残っている感があるんです。それはやはり、ちゃんと聴いてくださる方の手元に届いて、その瞬間に完成するアルバムを作ったんだな、という感じがしていて。だからリリースが本当に楽しみですね。

TEXT キャベトンコ
PHOTO Kei Sakuhara