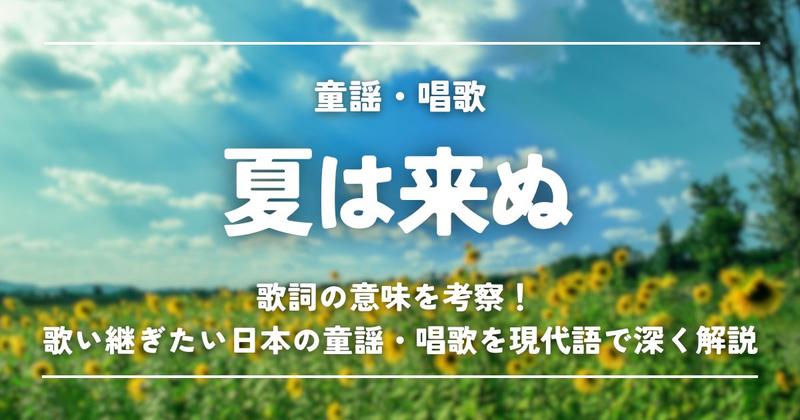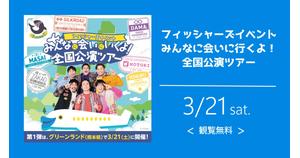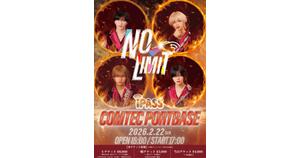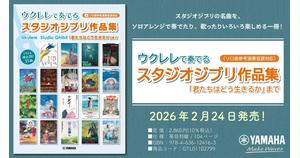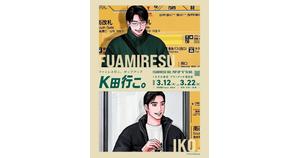「夏は来ぬ」は「夏が来た」の意味
 『夏は来ぬ』とは「夏が来た」の意味です。
『夏は来ぬ』とは「夏が来た」の意味です。『夏は来ぬ』の「ぬ」を否定の意味に捉えてしまい「夏が来ない」と解釈してしまうかもしれません。
実は「来ぬ(きぬ)」は「来た」の意味なのです。
来ない場合は「来ぬ(こぬ)」と表現するのが正解です。
現代の会話においてはあまり使われることがなく、聞きなじみがない言葉かもしれません。
俳句や短歌などでは今でも使用され、演歌の歌詞で使われることも。
情緒的な表現なので味わい深さを感じることができます。
「日本の歌百選」選出・夏の風物が豊富な歌詞
 『夏は来ぬ』は1900年(明治33年)に発表された童謡・唱歌です。
『夏は来ぬ』は1900年(明治33年)に発表された童謡・唱歌です。1940年(昭和15年)頃、NHKラジオの歌謡番組で放送され広く歌われるようになります。
第二次世界大戦後には、国定音楽教科書に掲載されました。(1番と5番のみ)
2007年には「日本の歌百選」に選出され、歌い継ぎたい童謡・唱歌として広く認識されています。
『夏は来ぬ』は、卯の花、時鳥(ホトトギス)、五月雨、橘、蛍、水鶏(クイナ)など夏の風物を織り込んだ歌詞が特徴的です。
「夏は来ぬ」歌詞の意味を現代語で考察
 明治33年に国文学者・歌人である佐々木信綱の作詞で発表された『夏は来ぬ』。
明治33年に国文学者・歌人である佐々木信綱の作詞で発表された『夏は来ぬ』。昔の言葉で書かれているので表現が難しく感じます。
『夏は来ぬ』の歌詞を、現代語で詳しく紐解いていきます。
----------------
卯の花の、匂う垣根に
時鳥、早も来鳴きて
忍音もらす、夏は来ぬ
≪夏は来ぬ 歌詞より抜粋≫
----------------
卯の花は別名をウツギと言い、初夏に花を咲かせます。
時鳥(ホトトギス)は、5月頃に中国やインドから日本へ渡ってくる夏鳥。
夏の季語として多く使用されます。
忍音とはホトトギスの初鳴きのこと。
「卯の花の香りが垣根に漂い、早くもホトトギスがやってきて初鳴きの声が聞こえる。夏が来たのだなあ。」
----------------
さみだれの、そそぐ山田に
早乙女が、裳裾ぬらして
玉苗植うる、夏は来ぬ
≪夏は来ぬ 歌詞より抜粋≫
----------------
さみだれ(五月雨)は梅雨時期の長雨、早乙女は田植えをする若い女性、裳裾は着物の裾のこと。
玉苗はみずみずしい若い苗の事で早苗(さなえ)とも表現できます。
元気な苗の様子から玉苗と名づけられました。
「五月雨が降る山の田んぼで、若い女性が着物の裾を濡らしながら田植えをしている。夏が来たのだなあ。」
----------------
橘の、薫るのきばの
窓近く、蛍飛びかい
おこたり諌むる、夏は来ぬ
≪夏は来ぬ 歌詞より抜粋≫
----------------
橘は日本の柑橘植物で、香りを楽しめるのは花の咲く5〜6月と実がなる11〜12月頃。
のきばは、家の屋根の下の部分、軒下のこと。
「おこたり諌むる」は、怠けることに対して忠告するという意味。
この部分の歌詞は、中国の故事「蛍雪の功」に由来するのではと言われています。
裕福ではない家庭で、蛍の光や雪の明かりで勉学に勤しんだという話。
「蛍雪の功」に関連する日本の歌では『蛍の光』や『仰げば尊し』が有名です。
「橘の香りが漂う軒下。窓の外では蛍が飛び交い、怠けずに勉強しろよと諫められているみたいだ。夏が来たのだなあ」

----------------
棟ちる、川べの宿の
門遠く、水鶏声して
夕月すずしき、夏は来ぬ
≪夏は来ぬ 歌詞より抜粋≫
----------------
楝(おうち)とは別名センダン(栴檀)のこと。初夏に淡い紫色の花をつけます。
クイナは文字通り水鳥。
クイナの鳴き声は「コッコッコッ」と門を叩く音に例えられ、主に夕方から夜にかけて鳴きます。
「センダンの花が散る川辺の家。門の外ではクイナの鳴き声がする。夕方になると涼しげに月が浮かんでいる。夏が来たのだなあ。」
----------------
五月やみ、螢飛びかい
水鶏なき、卯の花咲きて
早苗植えわたす、夏は来ぬ
≪夏は来ぬ 歌詞より抜粋≫
----------------
「さつきやみ」とは5月の夜、すなわち初夏の頃の夜。これまでの歌詞に登場した蛍、水鶏、卯の花、といった言葉が並びます。
「初夏の夜、蛍が飛び交い、クイナが鳴き、卯の花が咲き、早苗が広く植え渡った。夏が来たのだなあ。」
「夏は来ぬ」歌い継ぎたい日本の原風景
 『夏は来ぬ』は、初夏の風物を豊富に織り込んだ童謡・唱歌で「日本の歌百選」にも選出された名曲です。
『夏は来ぬ』は、初夏の風物を豊富に織り込んだ童謡・唱歌で「日本の歌百選」にも選出された名曲です。日本の原風景を思い起こさせるような、情緒的な歌詞が特徴的です。
古い言葉だからこそ響く歌詞、メロディーの素晴らしさがあります。
現代の言葉で紐解くと、初夏の頃を歌った歌詞の趣を深く感じることができるでしょう。
ぜひ、歌詞の意味を考察しながら聴いてみてください。