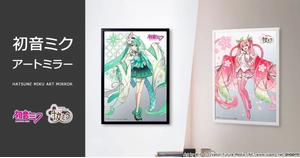金子ノブアキ「Historia」
Weather and Seasons
何年か前のドラムセミナーで(もちろん私はドラムに触ったこともない)シェイカーと自分とが違う拍子を刻んでいる。シェイカーのほうはこっちにつられないように必死になってと、笑って解説していた。もちろんそこに嫌味は全くない。
彼はかの天才ピアニストリストの如く、その超絶テクを見せつけたかったわけではない。
歌詞の意味ははっきりとは計り知れないが、同じミュージシャンとして先輩であり仲間であり、そしてなによりも父親であるジョニー吉長を失った悲しみを表現するには、この不思議なリズムの造形が普通に必要だったのだろう。
穏やかなメロディーと誤差なく構築された正確無比なストロークの調和が美しい作品である。
「Call My Name」
ドラマーとしての技術へのこだわりが全く感じられない作品。当たり前すぎるメロディーにのせた日常会話のようなボーカル。そこに差し込むように組み込まれたエレクリックな音。ある意味、無音の不協和音というべき空気感―身体全体で絶妙な重なりを見せる間接照明を浴びるような感覚が心地いい。
決してナチュラルとはいえない人工的な味わいしか発生させていないのに、本当の自分を預けられる確かな時間が注ぎ込まれる風景を体現できる。
「Ranhansha」
このアルバムのカオというべき作品。彼のドラムは、単に音を大きくすべく付け足されるものではなく、曲全体を抑え込み、まとめあげていく司令塔のような役割を果たす。激しいストロークでありながら、それが始まり―終了という単なるアクションではなく、過去→現在→未来という時空を超えた多様なワーキングへと展開する。
後半、うねるようなギターが迫ってくるが、真っ向から勝負するのではなく、逆に美しく映し出す波となって静かに揺らぐかのようなギアチェンジが施される。金子ノブアキの男気のなかの一瞬の“泣き”が光る。
「Sad Horses」
雄の香りというエロスと、名も知れぬ森に1頭の馬が走っているというファンタジー感。この両者の並行が、目の前に柔らかな油絵のような映像美を創り出す。彼のボーカルはより穏やかで普通過ぎる。ボーカリストとしての欠如というよりも、むしろ大人の穿った対応と感じる。
そのせいか、彼のドラムはテクニックという絶対的なものではなく、ボーカルと一体となって、軽くつかみやすいものとしてリスナーに語りかけてくる。他のドラマーにはない、潔さを感じる。
そして気になるのがこの曲のエンディングである。約2分半もの間、尾を引くような長いキーボード音が続く。
この曲のテーマをぶち壊すこともなく、この曲に描かれたストーリーに、何か特別の脚色を与えているわけでもない。
しかしこのエンディングがなかったら、“男のロマン”という閉鎖的空気だけしかない楽曲になっていたのは確かだ。
この不思議なテールがあることで、この曲の鍵が外され、立ち入りが許可され、解放感と華やいだ雰囲気が発生している。実に画期的な演出と言える。
「The chair」
空を突き抜けるような勢いのあるサックスと、ナッツを砕くようなパーカッションが、程よい太陽光あふれる初夏の清々しさを感じさせる。世界中のすべてのスイッチがONされ、朝の始まりの、無数の靴音、電車の騒音といった街中にあふれる“次なる音”をすべて集めたような喧噪。
男臭い金子ノブアキからは想像できない、どこか女性的な繊細な音の構築にただ驚く。
後半、エフェクトの効いた穏やかなボーカルが入り、このままさわやかな“うた”にシフトチェンジするのかと思うと、それまで緩やかに広がりを見せていたキーボード音がスパークルしていき、朝の始まりから、来たるべきその先の希望と混沌、予兆といったものへと変化していく。
「HISTORIA」のラストの曲として締めくくっているのか。それとも開けるべき扉なのか。精神のざわめきを覚える問題作といえる。
まとめ
「Historia」はリリースから4年になるが、聴くたびに開封時のラッピングカット音のする新品の冷たさをキープしている。無駄な音を捨てるのではなく、最初から無駄な音なんてなかったレベルのスタジオワークが、この作品の経年劣化を阻んでいる。
それを、あたかもAIが創造したかのようなデータの集合体と見るか。あるいは、頑固職人の握った寿司の如くスキのない美意識と見るか。
金子ノブアキのイズムはその両者それぞれに等しく振り切っている。
TEXT:平田 悦子