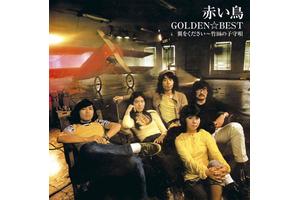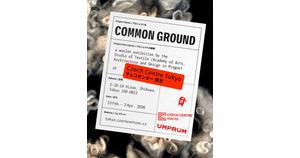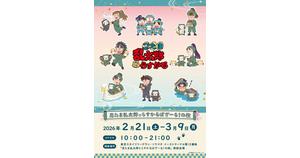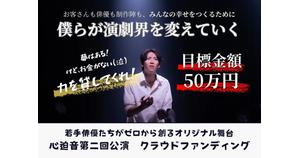フォークグループ・赤い鳥が広めた京都民謡は守り子唄

日本のわらべ歌は制作当時の背景を映し出すと共に、時代が移り変わっても聴けば自然と懐かしさを覚えるものですよね。
『竹田の子守唄』もそのひとつで、京都府の民謡として明治時代中期頃から口伝えに広まっていきました。
そして、1971年にフォークグループ赤い鳥が歌詞とメロディを変更しシングルのA面として発売。
これがきっかけとなり、『竹田の子守唄』は日本中で知られるようになりました。
タイトルの「竹田」は京都市伏見区竹田地区のこととされており、その地域住民によって生まれた曲のようです。
またタイトルに「子守唄」とつけられていますが幼児を寝かしつける時の歌ではなく、正しくは子守奉公として働いていた10歳前後の少女が自身の心境を歌った“守り子唄”です。
フォーク歌手らの演奏により人気を集めた『竹田の子守唄』ですが、後に放送局から自主規制され放送禁止歌として長らくメディアで歌唱される機会が減少した時期もありました。
守り子のどんな気持ちを歌っているのか、なぜ放送禁止歌となってしまったのかを理解するため、歌詞の意味を考察していきましょう。
----------------
守もいやがる 盆から先にゃ
雪もちらつくし 子も泣くし
≪竹田の子守唄 歌詞より抜粋≫
----------------
冒頭から「守もいやがる」、つまり子守奉公の仕事にうんざりしている様子が描かれています。
それは盆から先の時期は雪が降り、寒さからか子守をしている赤ん坊もいつも以上によく泣いて世話が大変だからのようです。
夏真っ盛りの盆の時期では雪には早すぎるという意見もありますが、貧しく満足な防寒ができたとは思えない守り子たちはどれほど寒さに耐えられる環境にあったでしょうか?
さらに自身もまだ幼い身であるにも関わらず学校にも行けずに親元を離れて働く少女のつらさを考えれば、愚痴をこぼしたくなるのも頷けます。
そしてその気持ちはほかの守り子たちも同じだったのでしょう。
寂しさや苦しさが冬をより厳しく感じさせていることが窺えます。
貧しく苦労の多い守り子たちの日常

----------------
この子よう泣く 守をばいじる
守も一日 やせるやら
≪竹田の子守唄 歌詞より抜粋≫
----------------
「いじる」はいじめるという意味で、赤ん坊がなかなか泣き止んでくれないせいでいじめられているかのように感じていることが伝わってきます。
赤ん坊が泣くと奉公先の家族から叱られてしまうため、そのことを恐れているのでしょう。
相手は赤ん坊なので意図して守り子を困らせているわけではありませんが、そのことを受け止めるには少女はまだ幼すぎるのです。
こんな大変なお守りを一日中続けていたら痩せてしまうと、守り子の苦労を明かしています。
----------------
久世の大根飯 吉祥の菜飯
またも竹田の もんばめし
≪竹田の子守唄 歌詞より抜粋≫
----------------
「久世」や「吉祥」も京都にある地名です。
当時は白米だけを食べることが難しい時代だったため、全国的に白米に野菜を合わせたものが食べられていました。
それで久世では「大根飯」、吉祥では「菜飯」のような慎ましい食事が日常だったことを表しています。
それに対し、竹田地区で食べられていたという「もんばめし」とはおからと精米の欠片で炊いた非常に粗末な食事のこと。
竹田は大根飯や菜飯が食べられる久世や吉祥よりも、さらに貧しい地区であることを嘆いている歌詞ということです。
ただし実際の地名が使われているため、竹田地区の住民の人権を守る意味も込めてメディアではこの部分の歌詞を変更して歌われることもありました。
放送禁止歌になった理由は部落差別?
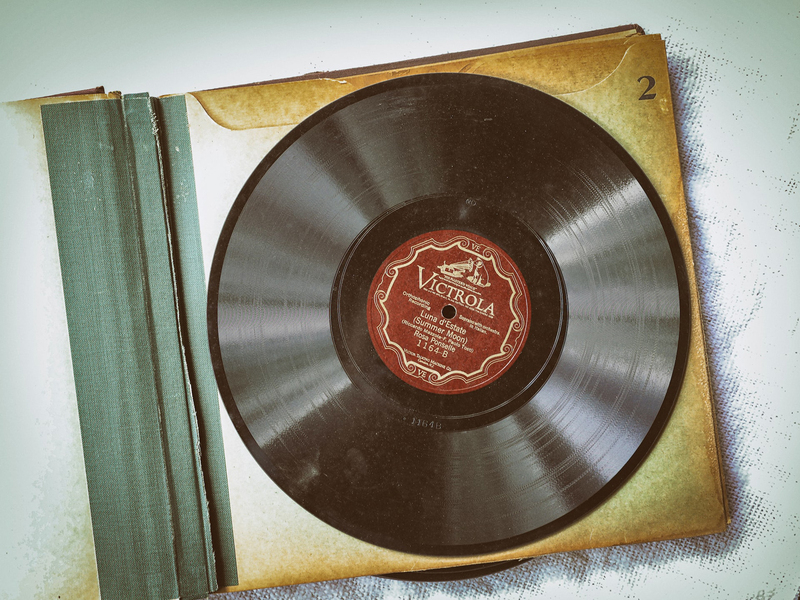
『竹田の子守唄』が放送禁止歌となった主な原因は、次の歌詞にあります。
----------------
はよもゆきたや この在所こえて
むこうに見えるは 親の家
≪竹田の子守唄 歌詞より抜粋≫
----------------
まず「はよもゆきたや」は早く行きたいという意味で、この部分は簡単に言えば「遠くに見える親の家に帰りたい」と歌っています。
それがなぜ放送禁止となったかというと、問題は「在所」の言葉にあったようです。
一般的に「在所」は故郷や田舎を指す言葉です。
ところが、「在所は被差別部落を意味するのでは?」という噂が広まってしまいます。
その点が問題視され、放送禁止歌となってしまったのです。
「在所」の意味をさらに調べると、今住んでいる場所のことを指す意味もあるようです。
そう捉えると単に子守奉公を終えて早く親元に帰りたいと歌っていると考察でき、よりしっくりくる内容と感じられます。
実際には目には見えないのに「むこうに見える」と歌っていることも、遠くにいる家族のことを目に浮かぶほど恋しく感じていることを伝えてきますよね。
1990年代に自主規制は緩和され、引き続き多くの歌手がカバーする名曲として現代まで歌い継がれてきました。
そこには日本の歴史と当時の人たちの心を大切にする、日本の良さが表れているように感じます。
日本のわらべ歌の美しさを感じよう
『竹田の子守唄』は誤解から一時メディアから消えてしまいましたが、歌詞をじっくり読み解くと、当時の厳しい生活を必死に耐えてきた女性たちの苦労と生命力が伝わる作品であることが分かるでしょう。それと同時に、曲の背景をよく知り多角的に考察することで理解が深まることも感じられます。
美しい音楽と日本人の想いが詰まったこの歌をぜひ後世まで残していきたいですね。