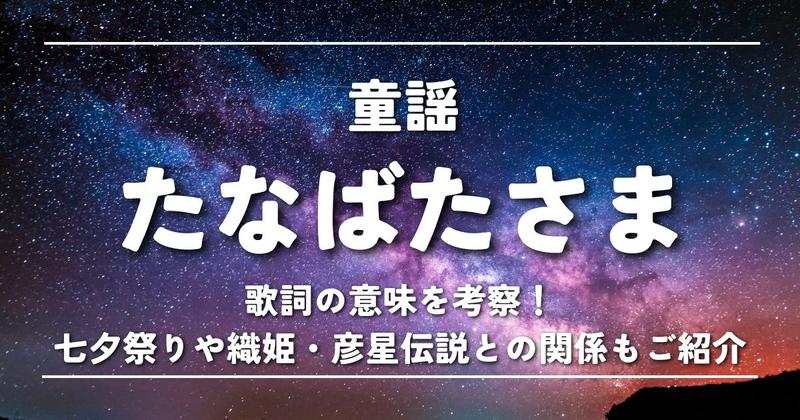七夕祭りの起源は?織姫と彦星の伝説

七夕は、中国神話に登場する織姫と牛郎の逢瀬を祝う中国の祭りが起源です。
機織りの織女と牛飼いの牛郎の恋物語は、日本では織姫と彦星の伝説として知られています。
働き者の二人が結婚を機に、牛飼い、機織りの仕事を怠るようになったため、天の神様の怒りを買い引き離されました。
悲しむ織姫を哀れに思った神様が「年に一度だけ会っても良い」と言いました。
こうして二人は年に一度、七月七日に会う事が許されます。
これが織姫と彦星の七夕の伝説です。
「たなばたさま」歌詞に込められた平和への想い

童謡『たなばたさま』の作詞は、明治生まれの作詞家・童謡詩人である権藤花代です。
作詞補助を詩人の林柳波が行っています。
1941年、第二次世界大戦中に「国民学校令」が制定されました。
『たなばたさま』は、音楽の教科書に載せるため、文部省が題材を指定し創られた歌と言われています。
『たなばたさま』の歌詞の意味を考察します。
----------------
ささの葉さらさら
のきばにゆれる
お星さまきらきら
きんぎん砂子
≪たなばたさま 歌詞より抜粋≫
----------------
歌詞に出てくる「のきば」は、漢字で書くと軒端で屋根の端っこのこと。
雨などをよける、ひさしとなっている部分です。
『たなばたさま』では、軒端に七夕飾りを飾っている様子が描かれています。
「きんぎん砂子」は、漢字で書くと金銀砂子。
金箔、銀箔を細かく砕いた粉の事を指します。
七夕の夜空に光る星たちを金銀の砂に例えた歌詞。
お星さまがキラキラした七夕の夜が目に浮かぶようです。
----------------
五しきのたんざく
わたしがかいた
お星さまきらきら
空からみてる
≪たなばたさま 歌詞より抜粋≫
----------------
「五しきのたんざく」とは、五色の短冊のこと。
五色の短冊に願いを書いて飾ると叶う、と言い伝えられています。
中国での五色は「青(緑)、赤、黄、白、黒(紫)」を指し、たいせつな行事で多く使われています。
中国では、万物は「木(緑)・火(赤)・土(黄)・金(白)・水(黒)」の五種類の元素からなるという自然哲学の思想があるからです。
この思想は日本にも大きな影響を与え、七夕のほか、こいのぼりなどの行事で五色が用いられています。
歌詞の中の「わたし」は、短冊にどんな願いを書いたのでしょうか。
戦時中に創られた歌詞には、平和への願いが込められている気がしてなりません。
「たなばたさま」歌詞に秘められた言葉遊び

----------------
きんぎん砂子
五しきのたんざく
≪たなばたさま 歌詞より抜粋≫
----------------
『たなばたさま』では、歌詞に言葉遊びが秘められているのです。
1番の終わりが「きんぎん砂子」で「ご」で終わり、2番の歌詞は「五色のたんざく」の「ご」で始まっています。
これは意図的に音をそろえたものと言われています。
----------------
ささの葉さらさら
お星さまきらきら
≪たなばたさま 歌詞より抜粋≫
----------------
「ささの葉さらさら」や「お星さまきらきら」など、句の終わりに同じ音を繰り返す脚韻という技法も使われています。
こういった言葉遊びの技法は、イギリスの童謡、歌唱の総称「マザー・グース」で多く使用されており、『たなばたさま』も影響を受けて創られたのでは、と言われています。
子ども向けに作詞された『たなばたさま』。
楽しく歌ってほしいと考え、創られたのかもしれません。
「たなばたさま」は歌詞が奥深い童謡
『たなばたさま』の歌詞には、中国の祭りである七夕由来の言葉が含まれています。歌詞の意味を考えながら聴くと、より深く情景が浮かんできそうです。
また、戦時中に創られた歌ということで、平和への思いが込められている気がしてなりません。
七夕の日には、織姫と彦星の伝説にも想いを馳せ、夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。