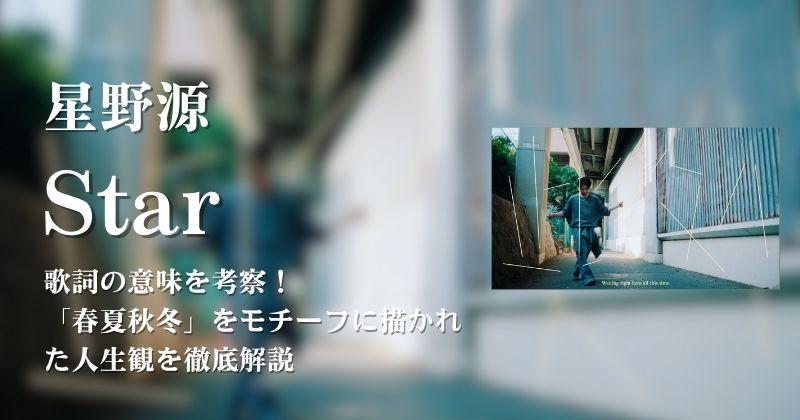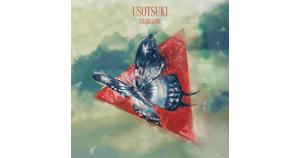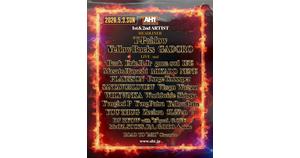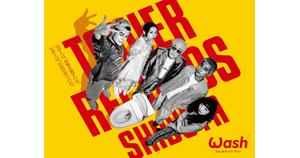春夏秋冬と人生がリンクした歌詞に注目
星野源の『Star』は、春・夏・秋・冬と移りゆく季節の変化を、人生とリンクさせ描いた歌詞が印象的です。人生観や死生観をテーマにしていますが、重くならないポップなサウンドに仕上げている点に、星野源の高い音楽性を感じます。
----------------
柊に咬む月
燻されて 拾う種に
祈り芽が成る
回る日の煌
陽気立つ温度が
胸がもう騒ぐ
あぶない季節
≪Star 歌詞より抜粋≫
----------------
春は芽吹きの季節。
人生で例えるなら産まれた瞬間や進学、就職など始まりの季節です。
冬は終わりの季節と言え、そしてまた春が巡ってくる。
そんな風に『Star』は人生を春夏秋冬に例えて描かれています。
冒頭で描かれるシーンでは明確な季節はわかりません。
しかし、柊という言葉が出てくることから、季節は秋から冬だと推測できます。
そして、春の部分につながっていく。
春から始まるのではなく、秋冬から春につなげるということに、星野のセンスを感じます。
「柊に咬む月」では、秋冬のピンと張りつめた夜空を感じることができます。
空気が乾いた季節だからこそ葉や枝も落ち、そしてまた命を宿す。
「燻されて 拾う種に祈り 芽が成る」の歌詞では、新たな命の始まりを想像させます。
命の始まりは、希望や夢や愛と言い換えてもよいのかもしれません。
「回る日の煌 陽気立つ温度が 胸がもう騒ぐ」では、日に日に暖かくなり心がワクワクしている様子を感じます。
「祈り」「種」「芽」という言葉から、春の始まりを予感させます。
人生に例えるなら、新しい命の始まりや、夢や希望に心を弾ませている瞬間と言えるのではないでしょうか。
「Star」春・夏パートを深掘り

----------------
君をずっと待ってた
此処でずっと待ってた
春は無駄を連れ
いのちは輝いた
花が咲き舞っては
影は美を創った
変わるこの星で
始を手に
≪Star 歌詞より抜粋≫
----------------
「君をずっと待ってた」の歌詞は、人によってさまざまな捉え方ができると思います。
例えば、新しい命の誕生を待ち焦がれる両親の姿、運命の人との出会いや再会を待つ人です。
「始を手に」の歌詞には、花が咲き乱れる春という季節に、新たな始まりを手にした喜びが描かれていると感じます。
春を待ち続けた寒い冬があったからこそ、より春の喜びが増す。
春につながる冬の季節は希望の時と言ってもよいのかもしれません。
----------------
海霧の向こうに
飛び乗って 笑う旅に
雲が流れる
愛と塵よ
重なれ盆棚
胸が高鳴る
醒めない季節
≪Star 歌詞より抜粋≫
----------------
「海」「雲」という言葉が夏を感じさせます。
「笑う旅に」の部分は「笑う度に」のダブルミーニングがあるのでは、と推測します。
歌詞を見ずに耳だけで聴いていると、おそらく「笑う度に」と認識する人が多いのではないでしょうか。
歌詞を見て気づいてほしいという、星野の遊び心かもしれません。
「盆棚」という言葉に命のつながりを感じます。
盆棚とは、お盆の時期に先祖の霊をお迎えし供養するために、お供え物や提灯を設ける棚や台のこと。
ご先祖様や故人と、今を生きる人々とをつなぐ、架け橋のようなものと言ってもいいのかもしれません。
「重なれ盆棚」の歌詞は、命のバトンをつなぐといった意味や、死生観を感じる部分であると言えるのではないでしょうか。
----------------
君をずっと待ってた
此処でずっと待ってた
夏が雨露をくれ
いのちは輝いた
花が咲き舞っては
影は美を創った
焼けるこの星で
詩を手に
≪Star 歌詞より抜粋≫
----------------
春に芽吹いた命が、夏の雨露でさらに輝きを増していく様子が描かれています。
「花が咲き舞っては 影は美を創った」の部分では、太陽の強い陽射しによって起こる影とのコントラストを表現し、焼けるような暑さの中、生きている生命力を感じます。
春の部分では「始を手に」の部分が、夏パートでは「詩を手に」となっています。
「詩」はさまざまな捉え方があると思いますが「自分だけの言葉」すなわち「自分だけの生き方」と解釈してもよいのかもしれません。
「Star」秋・冬パートを深掘り

----------------
瞼色 どの空も
秋が恋を告げ
いのちは輝いた
花が咲き舞っては
影は美を創った
塞ぐ冬を開け
私を手に
好きを源に
≪Star 歌詞より抜粋≫
----------------
秋パートでは、実りの季節が描かれています。
瞼色とはピンクや赤色の比喩。
秋は、果実や作物が実り、木々も赤く色づき成熟する季節。
人間を秋に例えると、成熟した壮年時代を描いていると言えるでしょう。
「冬を開け」の歌詞には秋の終わりを感じます。
となれば冬は人生に例えると老年期。
最後まで歌詞を紐解いてみると『Star』では、春夏秋冬を人生に例えて描いていることがよくわかります。
秋から冬に移りゆくパートでは「しを手に」の部分が「私を手に」となっています。
ここでは「私」という人間の自己の確立を感じるのです。
いろいろな経験を元に自分だけの人生を描き「私」という唯一無二の存在を創る、私らしく生きる、そういったメッセージが込められているのでは、と感じます。
「好きを源に」は、好きなことへの情熱や愛を元に人生を生きる、それがモチベーションになる、ということを伝えたい部分だと考察します。
さらに「源」を「みなもと」ではなく「げん」と言っている点が、星野ファンを沸かせている部分。
「ほしのげん」なのですから「好きをげんに」って、クスっとしてしまいませんか?
そして、ラストパートでは「終わるこの場所で わたしは輝いた」「生きるこの星で 死を手に」と結ばれています。
『Star』の歌詞を最後まで紐解くと、壮大なストーリーを読んだ感じがします。
人生が終わる瞬間に、どれだけ自分の人生を輝かせることができたのか、どれだけ自分が納得して生きられたのか。
それを感じる事ができるのならば、幸せな人生だったと言えるのではないでしょうか。
春では「始を手に」。
夏では「詩を手に」。
秋から冬では「私を手に」。
この部分が最後には「死を手に」となっています。
さまざまな「し」を入れる部分での言葉のチョイスが『Star』の核の部分とも言えるでしょう。
そして、なぜタイトルに『Star』とつけたのか。
宇宙には数えきれないほどの星が存在すると言われています。
そんな無数の星の中で、自分だけの星を輝かせる、すなわち唯一無二の、自分だけの人生を輝かせることに意味がある、と思うのです。
誰もが最後は夜空の星になる、だからこそ命ある限り輝く「Star」になろう、というメッセージが『Star』にはあるのではないでしょうか。
「Star」は星野源の死生観が心に響く楽曲
星野源の『Star』は、歌詞を春・夏・秋・冬のパートに分け、四季を人生に例えた歌詞が印象的な楽曲です。大病を経験した星野源だからこそ書ける、彼の死生観や人生観を描いた楽曲が人々の心に響くのではないでしょうか。
また、歌詞に何度も出てくる「し」の部分を深掘りすると、さまざまな捉え方ができると思います。
日本文化に愛着を持っている星野が選んだ「盆棚」という言葉や、季節の移ろいについても注目して聴いてみてください。