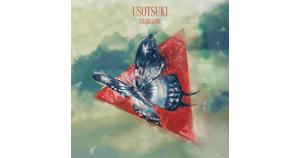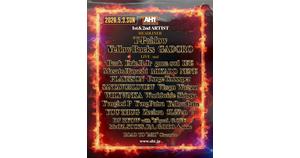西の扉にぶら下がるもの
Siipは2020年に突如現れた正体不明のシンガーソングクリエイターです。公式サイトには英語で「詳細は不明。Siipは、特定のイメージを持たない、捉えどころのない幻影的な表現者だ」と記載されています。
そんなSiipの1stアルバム『Siip』は2021年に発売され、「生命の根源に迫る壮大なストーリー」が話題になりました。
アルバム『Siip』の5曲目に収録されているのが『Walhalla』です。
タイトル通り北欧神話のヴァルハラがモチーフとなった楽曲になっており、2025年5月にはMVも公開されました。
MVは白いベールを被ったシスター姿の人たちがろうそくを持っている映像と共に『Walhalla』が混声合唱されます。
まさに「幻想的な表現」を体現したようなMVです。
そんな『Walhalla』のモチーフになっているヴァルハラは、最高神オーディンの館(大広間)を指します。
オーディンの館は戦場で勇敢に戦って死んだ戦士を迎えるための場所です。
最高神オーディンがなぜ、勇敢な戦死者をヴァルハラに集めているかといえば、来る最終戦争「ラグナロク」に備えてのことでした。
Siipが歌う『Walhalla』の歌詞にはこの「ラグナロク」に関してぼやかした表現がなされています。
勇敢に死んだ戦士が迎えられる場所を、あたかも天国のように描くのが『Walhalla』です。
その理由は『Walhalla』という曲の公開が2021年というコロナ禍真っ只中であり、誰もが自宅という場に留まらざるを得なかった現実を写しているのかも知れません。
しかし、Siipのコンセプトは「特定のイメージを持たない」ことです。
歌詞の考察をする事自体がSiipのコンセプトからは離れてしまうかも知れませんが、一つの解釈として受け止めていただければ幸いです。
----------------
力任せに負けたわけではない
戦士は花の飾りが邪魔になった
西の扉にぶら下がるのは何故?
また膿んで 搾り取って 血を止める為の血肉が足りない
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
ヴァルハラに行く条件は、勇敢な戦死者であることです。
この戦士は「力任せに負けたわけではない」ですが、ヴァルハラに迎えられたので、勇敢な戦士です。
「花の飾りが邪魔になった」ともあります。
戦士は一般的に市民のために戦っていますから、「花の飾り」を送ったのも市民なのでしょう。
そして、その「花の飾り」が邪魔に感じている、ということは戦士は市民のために戦っていたと言うよりは、戦場という場に立つことに意味を見出していたのでしょう。
明言はできませんが、戦士はまさにヴァルハラに行くために戦っていたのかも知れません。
続く歌詞は「西の扉にぶら下がるのは何故?」です。
「グリームニルの言葉」によると「西の扉の前に狼がぶら下がっていてその上空をワシが飛んでいる」とあります。
歌詞にある「西の扉にぶら下がるのは」狼であることが、ここで分かります。
しかし、なぜ狼なのでしょうか?
それは最高神オーディンの最期がフェンリルという狼に飲み込まれる、と予言されているからです。
この「狼との戦い」が最終戦争であるラグナロクを指します。
戦士はヴァルハラに招かれ、狼がぶら下がっているのは何故? と疑問に思います。
しかし、それに答えてくれる人はなく、「また膿んで 搾り取って 血を止める為の血肉が足りない」と歌詞はつづき、戦士の肉体がもう保てなくなっていることが分かります。
ここで注目すべきは、西の扉にぶら下がっているはずの狼に歌詞は言及していないことです。
戦士がヴァルハラに迎えられた理由が狼と戦うこと、ラグナロクだと伝えられていないのでしょう。
上空を飛んでいるもの

----------------
こんなにもめでたい事はない
喜びの館にて騒ぎましょう
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
戦士は「こんなにもめでたい事はない」と歓迎されています。
歌い出しのフレーズで「花の飾りが邪魔になった」戦士です。
戦う気満々でいたはずですが、いざ望んだヴァルハラに招かれると「喜びの館にて騒ぎましょう」と誘われます。
----------------
ほら、酒を浴びて
鎧を脱いで
勇敢に散って逝った僕らを
父は 優しく撫でて
惰性を許して
終焉の日まで
楽しむの
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
ここで登場した父は、最高神オーディンでしょう。
そして、「僕ら」というキーワードもありますので、「花の飾りが邪魔になった」戦士以外にも勇敢に戦った戦死者がいることが分かります。
彼らは「酒」を与えられ、「鎧」を脱がされ、最高神オーディンに「優しく撫で」られます。
更に、「惰性」を許し、「終焉の日まで」「楽しむの」だといいます。
もはや、父である最高神オーディンは戦士たちに戦うことを望んでいません。
----------------
剣で編み物
土だけじゃ飢餓は減らないけど
花の名前を知りたくなった
屋根は楯でその上を飛ぶのは誰?
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
最高神オーディンが戦いを望んでいないヴァルハラでは剣は「編み物」の道具と化しています。
「土だけじゃ飢餓は減らないけど」「花の名前を知りたくなった」とあり、知識欲が芽生え始めていることも分かります。
その後に「屋根は楯でその上を飛ぶのは誰?」です。
これは『Walhalla』の中で2つ目の「?」であり、前回と今回以外に「?」は出てきません。
では「盾」の上を飛んでいるものはなんでしょうか?
「西の扉」で引用した一節をもう一度見てみましょう。
「西の扉の前に狼がぶら下がっていてその上空を鷲が飛んでいる」
「グリームニルの言葉」をそのまま真に受けるなら、「盾」の上を飛んでいるのは「鷲」です。
しかし、やはり「鷲」だと明確な言及は避けます。
父の為に強くなる

----------------
こんなにも恵まれた事はない
最期を戦場で迎えたの
こんなにも黄金がある処
他には知らないよ 幸福の場所
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
戦士は「剣で編み物」をするようなヴァルハラに順応し、「こんなにも恵まれた事はない」と思います。
戦場で最期を迎えたことによって「こんなにも黄金がある」「幸福の場所」へ行けるなんて、と感嘆しています。
その姿には生前の「花の飾りが邪魔になった」姿はないように思えます。
----------------
父の為に強くなる
此処は天国
終焉の日まで
腕を磨くの
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
戦士たちは「花の名前を知りたくなった」はずですが、ここに来て「父の為に強くなる」という本来のヴァルハラの目的に回帰します。
知性は芽生えず、ただ、「終焉の日まで」「腕を磨くの」だ、という結論に達します。
勇敢な戦士はどこまでいっても、戦士だったということなのでしょう。
----------------
ほら、酒を浴びて
鎧を脱いで
勇敢に散って逝った僕らを
父は いつも称えて
この広いヴァルハラで
終末の日まで
楽しむの
≪Walhalla 歌詞より抜粋≫
----------------
前半の繰り返しです。
ただし、部分的に変わってもいます。
「勇敢に散って逝った僕ら」に対して、前半では「父は 優しく撫でて」「惰性を許して」くれていました。
しかし、今回は「父は いつも称えて」「この広いヴァルハラで」となっています。
父である最高神オーディンは戦士が欲するものを常に与えています。
ヴァルハラに来た当初は「惰性を許し」ており、腕を磨きはじめると「いつも称えて」くれます。
そして、「この広いヴァルハラで」です。
表記はカタカナで、タイトルのWalhallaとも異なります。
歌詞の中のこのヴァルハラは最後のこのフレーズのみです。
勇敢に散った戦士が迎えられる場所という意味では、一般的な「ヴァルハラ」と一致していますが、そこにあるイメージとは異なる楽園として『Walhalla』の歌詞は描かれています。
Siipという「特定のイメージを持たない」ことをコンセプトにしたシンガーソングクリエイターだからこそ、新しい『Walhalla』像をここに打ち出そうとしたのかも知れません。
すでに神話として凝り固まったイメージのあるものを敢えて選び、戦士たちが過酷な戦いに身を投じるはずの結末を「終末の日まで」「楽しむの」と締めるSiipには、物事は見え方を変えることで楽園になる、と言いたいようにも見えます。
終末の日まで
『Walhalla』の歌詞に登場する戦士たちは結局、剣を手にしています。「剣で編み物」をし続ける未来もあったはずですが、彼らは生前と変わらぬ生活をヴァルハラでも続けています。
人はそんなに簡単に変わることはできないのでしょう。
変わらないことが悪いわけではありません。
最高神オーディンはそれも肯定しています。
変わらないからと言って、同じことの繰り返しで良いわけではありません。
「終末の日まで」「楽しむ」コツは変わって、戻ってを繰り返すこの連続性にこそ意味があるのかも知れません。
ヴァルハラという一見すれば日常から程遠い歌詞に思えますが、『Walhalla』は日常を変えたい人や変われなかった人を優しく包み込むような内容でもあります。
日常の変わらないものを前にした時、「楽しむ」ための方法を『Walhalla』を聞いて考えてみるのも一興ではないでしょうか。