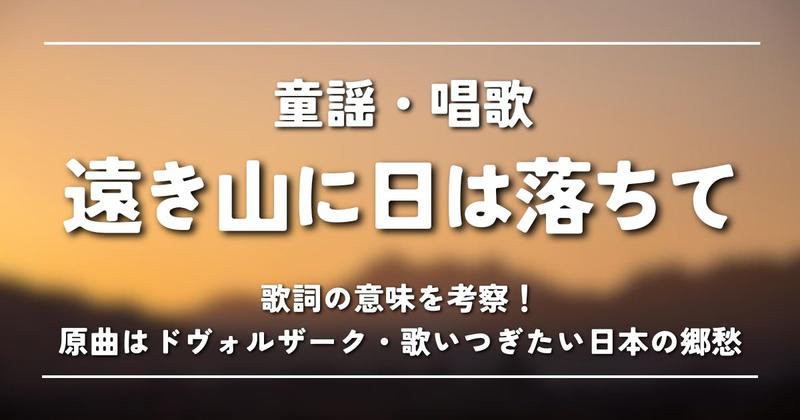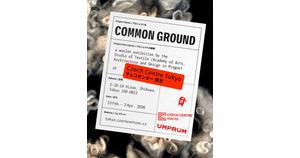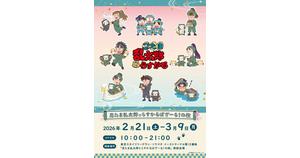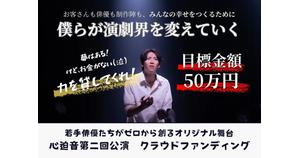「遠き山に日は落ちて」原曲はドヴォルザーク「新世界第2楽章・家路」
『遠き山に日は落ちて』は、日本では童謡・唱歌として知られている楽曲です。教科書に長年採用され、下校時間や市町村の夕方のチャイムで使用されたりと、とても身近な存在。『遠き山に日は落ちて』を聴くと「下校時間だ」「家に帰らなくちゃ」など焦った記憶があるかもしれません。歌詞の出だしが「遠き山に日は落ちて~」であることも関係してか、夕方を知らせる曲として定着しています。『遠き山に日は落ちて』の原曲は、チェコの作曲家ドヴォルザークが1893年に作曲した交響曲第9番「新世界より」の第2楽章「ラルゴ (Largo)」です。そして、第2楽章の主題となる旋律に基づいて、ドヴォルザークの弟子フィッシャーが作詩・編曲したものが「新世界第2楽章・家路(Goin' Home)」です。「新世界」は全4楽章あり、音楽の授業で学んだ人も多いのではないでしょうか。第2楽章を元にした「家路」は、ゆったりとした美しい旋律で夕刻の訪れを醸し出しています。
この「家路」に歌詞をつけたのが、作詞・作曲・訳詩家、音楽評論家の堀内敬三です。1947年に現:全日本音楽著作家協会の初代会長に就き、ラジオのクラシック音楽番組の司会を務めるなど、日本の音楽界において著名な人物です。『遠き山に日は落ちて』が初めて音楽の教科書に載ったのは1962年で、以降、誰もが知る名歌として親しまれています。
「遠き山に日は落ちて」1番の歌詞を考察

----------------
遠き山に 日は落ちて
星は空を ちりばめぬ
きょうのわざを なし終えて
心軽く 安らえば
≪家路<遠き山に日は落ちて> 歌詞より抜粋≫
----------------
「遠き山に 日は落ちて」この歌詞だけで、夕暮れ時が目に浮かびます。近くの山ではなく、離れた山に夕日が沈んでいく。辺りはうっすら茜色に染まり、叙情的な雰囲気が感じ取れます。夕日が沈み、空には星が散りばめられていく。夕暮れから夜へと変わる幻想的な風景が浮かびます。「きょうのわざ」とは、今日やるべきことでしょう。今日の仕事をやり終え、心がホッとしている様子です。
----------------
風は涼し この夕べ
いざや 楽しき まどいせん
まどいせん
≪家路<遠き山に日は落ちて> 歌詞より抜粋≫
----------------
『遠き山に日は落ちて』を聴いて、思い浮かべるのは日本の原風景ではないでしょうか。子どもたちが虫取りや、水遊びからそれぞれの家へ帰っていく。大人たちは、畑仕事を終え汗を拭きながら家路につく。なぜか、夏のシーンを思い浮かべてしまうのは「風は涼し この夕べ」とあるからなのだと気づきます。子どもも大人もやるべきことが終わり、夕方を迎える。涼しい風が吹き、今から家族で夕食の時間となる。
「まどいせん」とは、人々が集まり輪になって座り、語り合う様子のことです。漢字では「円居せん」と書き、主に家族や親しい友人同士が集まって楽しい時間を過ごすという意味で使われます。1日の用事をすませ、これから家で楽しい時間が始まるというという温かい雰囲気を感じます。家=故郷ととらえることもでき、故郷を離れている人にとって『遠き山に日は落ちて』は、郷愁を思い起こさせる楽曲かも知れません。
「遠き山に日は落ちて」2番の歌詞を考察

----------------
やみに燃えし かがり火は
炎今は 鎮まりて
≪家路<遠き山に日は落ちて> 歌詞より抜粋≫
----------------
かがり火とは、屋外での照明や防犯のために焚く火のこと。闇の中、燃えていた火が静まっていく事から、夜が深くなり眠りにつく時間が訪れていることを感じます。家の中を照らすろうそくの炎、ランプ、囲炉裏の火などを思い浮かべてもよいのかもしれません。いずれにしても、本格的な夜の訪れを感じ、安息の時間を迎えようとしている様子が感じ取れます。
小中学校時代にキャンプや合宿を体験した人は多いでしょう。その時に『遠き山に日は落ちて』を歌った記憶があるのではないでしょうか。かがり火は、今でいうならキャンプファイヤーと言ってもいいかもしれません。そして、1番に出てきた歌詞「まどいせん」と組み合わせれば『遠き山に日は落ちて』は、楽しく火を焚いて語らうキャンプファイヤーにピッタリの楽曲だと言えそうです。
----------------
眠れ安く いこえよと
さそうごとく 消えゆけば
安き御手に 守られて
いざや 楽しき 夢を見ん
夢を見ん
≪家路<遠き山に日は落ちて> 歌詞より抜粋≫
----------------
本格的な夜を迎え「安らかにぐっすりと眠りなさい」と、誘う声。「楽しい夢を見てお眠りなさい」と言ってくれる手は誰の手でしょうか。『遠き山に日は落ちて』は日本の原風景が浮かぶと先に述べました。「安き御手」には「日本のお母さん」が思い浮かびます。いっぱい遊んで疲れた子どもの手を握り、やさしく「おやすみなさい」と言ってくれるお母さん。現代では多様性が求められ、子どもの世話は両親ともにする、というのが当たり前である世の中。昔ながらのお母さん、というのは通用しない時代なのかもしれません。でも、堀内敬三が作詞をした時代背景を考えると、どこの家庭にも当たり前にあったであろう、優しく穏やかな時間を感じるのです。
また、「神様の手」という意味もあるかもしれません。「家路(Goin' Home)」を作詞したドヴォルザークの弟子フィッシャーは、この歌に霊歌の意味も持たせ「Home」は家ではなく「故郷」と、キリスト教での死後に赴く場所「天上の故郷」として表現。こういった意味を踏まえると、1日の終わりに神様に今日のお礼を伝え、神様に見守られて眠りにつく、といった情景を思い浮かべることができます。優しい手に導かれ、静かで安心できる夜を迎えられることは、とてもとても幸せな事ではないでしょうか。
「遠き山に日は落ちて」は1日の終わりに聴きたいおだやかな郷愁を誘う名歌

『遠き山に日は落ちて』は、夕方のチャイムやメロディーで流れることが多いため、なんとなく寂しい曲と思っていませんか?実は、おだやかで幸せな夕方から夜のシチュエーションが描かれた楽曲なのです。1日の用事を終え、家族や友人と集まり夕食をとり、ゆっくりと眠りにつく。日常にある幸せな風景を描いた、郷愁を誘う日本の名歌です。