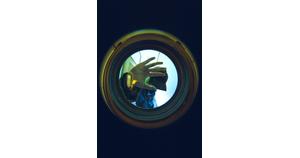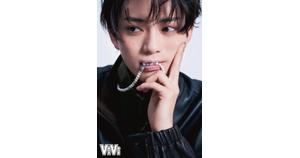枯れてしまった向日葵と、夕暮れに感じる暑さの余韻
本楽曲はアルバム『YANKEE』の、丁度折り返し地点である8曲目に配置されています。切なくも疾走感あふれる7曲目の『花に嵐』と、米津玄師節が色濃く現れる9曲目『しとど晴天大迷惑』に挟まれた『海と山椒魚』。
この曲はメロディアスなギターの響きと、跳ねるようなドラムのコントラストが美しく、その中で米津玄師さんの滑らかな歌声が映えます。
----------------
みなまで言わないでくれ
草葉の露を数えて
伸びゆく陰を背負って
あなたを偲び歩いた
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
歌詞では、「みなまで言わないでくれ」と誰かにお願いをしている様子から始まります。
続く「草葉の露を数えて」では”人命の儚さを数えてほしい”と、どこか空虚な雰囲気を感じさせます。
もしかしたら、近しい人を喪(うしな)った経験があったのかもしれません。
静かで寂しげな曲調ですが、人命に想いを馳せるところから、どこか温もりを感じる情景が浮かび上がります。
「伸びゆく陰を背負って あなたを偲び歩いた」とは、姿はなくとも”確かにそこに居た”。
影が伸びるという表現は、時の経過や夕暮れを思わせると同時に、どこか切ない孤独の余韻を漂わせます。
そんな雰囲気と感情だけを頼りに、前へと進んでいる様子が描かれているようです。
見えずともその人を想い続ける姿は、深くに入り込んだ「傷」のような存在にさえ思えますね。

----------------
二人で植えた向日葵は
とうに枯れ果ててしまった
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
そんな気持ちの中で、この悲しい向日葵の結末が登場します。
“枯れる”という表現は、花が一度しっかり咲いた後に訪れた終わりのように思えます。
この向日葵はただ咲かなかったのではなく、確かに花開く時があった。
さらには、その姿を二人で見届けた瞬間があったのだと想像できます。
だからこそ「枯れ果ててしまった」という言葉からは、築き上げてきた思い出が過去のものになってしまった喪失の傷みとして、鮮明ににじみ出ているように感じられます。
楽しかった日々があったからこそ、今の静けさや寂しさが胸に沁みるのでしょうか。
見えなくとも進んでいたことも否定される、「枯れた」存在によって、苦しい現実を突きつけられるようでもあります。
----------------
照り落ちる陽の下で
一人夏を見渡した
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
これまでは”向日葵”という夏のキーワードにとどまっていましたが、”夏”であることが言及され、情景を想像しやすくなりました。
向日葵が枯れ、記憶の中の誰かがいなくなった今でも、季節は変わらず巡り、太陽は何事もなかったかのように照りつけています。
その光の中で、かつてと同じ景色を見ているはずなのに、隣にいた人がいない。
その事実に気付いたときの、どうしようもない孤独感や取り残されたような感覚が、「一人夏を見渡した」という短い言葉に深く込められているように思います。
深い孤独の中で亡きあなたを想う”最後の祈り”

----------------
今なお浮かぶその思い出は
何処かで落として消えるのか
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
孤独を強く感じる人は、きっと孤独以外の温もりや繋がりも知っている人です。
強い孤独に苛まれるときは、そんな温もりを感じる。
つまりは、一緒に過ごした時間や言葉、景色の断片が、まるで波のように寄せては返すように、過去に想いを馳せる瞬間が繰り広げられます。
ここで問われているのは、その思い出が「どこかで落として」「消えて」しまう日は来るのか、ということかもしれません。
つまりは、自分の中からその人の面影が、本当に消えてしまう未来があるのか、という自問にも聞こえます。
忘れることが癒しになる場合もあれば、忘れたくないのに薄れていくことが、むしろ痛みになることもあります。
この一節には、そうした記憶と感情の間で揺れ動く、どうしようもない心の葛藤が浮かび上がってきます。
記憶を「落とす」という表現はとても印象的で、気付かない内に「どこかでポロっと落としてしまう」。
そんな不透明な喪失感が込められている言葉のように感じさせます。
----------------
あなたの抱える憂が
その身に浸る苦痛が
雨にしな垂れては
流れ落ちますように
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
この4行には、喪失を前にした“祈り”のような感情が込められているように思います。
ここで描かれるのは、すでに手の届かない「あなた」への思いやりで、自分がどんなに苦しくとも「相手の痛みがどうか和らいでいてほしい」。
そんな純粋で切なる願いのように思えます。
「憂」や「苦痛」という言葉に重ねられた感情は、すでに亡き人を想っているようにも、自分の元から離れていった誰かを想っているようにも読み取れます。
いずれにせよ、それは“今ここにいない人”への想いだと考えます。
関係が途切れてしまったからこそ、「せめてその苦しみだけでも癒えていてほしい」と願う気持ちは、言葉にならないほど深いものなのではないでしょうか。
そして、“雨”はしばしば浄化や癒しの象徴として描かれますが、ここでは、苦しみそのものが雨となって地に落ち、やがて洗い流されていくようなイメージが広がります。
“祈ることしかできない”状況の中で、それでもできる限りの優しさを差し出そうとしている。そんな不器用で、けれど真っ直ぐな想いがこの一節に込められているように受け取りました。

----------------
真午の海に浮かんだ
漁り火と似た炎に
安らかであれやと
祈りを送りながら
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
真昼の海という、陽光がまぶしく照り返すはずの時間帯に「漁り火と似た炎」が浮かぶという不思議な情景が描かれています。
「漁り火」は本来、夜の海に灯されるもので、そこに重ねられた「炎」は、おそらくもう会えなくなった“あなた”の存在そのもの、もしくはその魂のような象徴かもしれません。
そして「安らかであれやと 祈りを送りながら」という言葉からは、相手の苦しみを救いたいという思いと、もう二度と会えないという受け入れが、静かに共存しているように感じられます。
どれほど痛みを抱えていても、それでも最後に願うのは、「あなたが安らかであること」なのでしょう。
それは、愛が終わったあとに残る最も純粋な気持ちであり、死別や別れを経たあとに人がようやくたどり着く感情かもしれません。
『山椒魚』の改稿に重ねた、語り手の変化と祈り

----------------
みなまで言わないでくれ
俺がそうであるように
あなたが俺を忘れるなら
どれほど淋しいだろう
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
ここで再び「みなまで言わないでくれ」という言葉が登場します。
冒頭と同じフレーズが繰り返されることで、語り手の心がいまだ変わらぬ場所にとどまり続けていることが、静かに示されているように感じられますね。
「俺がそうであるように」という言葉には、語らないことを選んだ自分自身への静かな肯定、あるいは苦しい諦めのようなものが滲んでいます。
それと同時に、「あなたが俺を忘れるなら どれほど淋しいだろう」と続く一節からは、誰かの記憶から消えてしまうことへの恐れと、拭いきれない孤独感が浮かび上がってきます。
この矛盾するような感情の重なりが、どうしようもなく”人間らしさ”として胸に迫ってきます。
それは、別れや喪失を経験したあとに残る、極めて個人的で、けれど誰しもが抱えうる感情なのではないでしょうか。
----------------
岩屋の陰に潜み
あなたの痛みも知らず
嵐に怯む俺は
のろまな山椒魚だ
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
ここでついに登場する「山椒魚」という言葉。
それは、語り手自身を象徴する比喩として用いられています。
井伏鱒二の短編小説『山椒魚』では、成長しすぎた山椒魚が岩屋から出られなくなり、狭い空間に閉じ込められたまま外の世界をただ眺めることしかできなくなります。
やがて孤独と苛立ちから蛙を閉じ込め、共に過ごすものの、互いの痛みは理解されないまま、虚しさだけが残っていく。そんな閉塞感に満ちた物語でした。
しかし、後から著者本人によって救いのある結末へと書き換えられました。
改稿後は、蛙が弱り果てる中で、山椒魚は「もう降りてきてもいい」と声をかけ、蛙も「怒ってはいない」と答えます。
直接の和解とは言えないものの、そこには確かに“許し”と“共感”の芽のようなものが感じられるのです。
蛙だけの芽でなく、自分の殻に閉じこもって他者を遠ざけていた山椒魚も、ようやく誰かに手を差し伸べようとした。
それは2人にとって、微かな希望が生まれた瞬間でもあります。
本楽曲『海と山椒魚』においても、語り手は「岩屋の陰に潜み」「あなたの痛みも知らず」と語り、自身の弱さや後悔を赤裸々に見つめています。
けれど、それをただの自己憐憫で終わらせず「のろまな山椒魚だ」と自嘲しながらも、自分の声や歌で誰かの痛みを和らげたいと願っています。
そこには、この曲なりの“改稿”とも呼べる救いが、静かに差し込んでいるのではないでしょうか。
井伏の山椒魚が最後に赦しの言葉を交わすように、この歌もまた、語り手なりのやり方で、「失った誰か」に祈りを送り、ようやく“外の世界”へ向かおうとしているのかもしれませんね。

----------------
零れありぬこの声が
掠れ立ちぬあの歌が
風にたゆたうなら
あなたへと届いてくれ
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
そんな救いや祈りが込められた末に、ようやく語り手は「声」と「歌」に自分の想いを託します。
「零れありぬこの声が 掠れ立ちぬあの歌が」とあるように、ここでの“声”や“歌”は、形にならない想いの残響のようにも感じられます。
たとえ完全な言葉にはならずとも、外へと放たれようとする不完全な「叫び」として昇華されているようです。
それらが「風にたゆたうなら あなたへと届いてくれ」という祈りに繋がるのは、まさに“みなまで言えない”感情の極みであり、言葉にならない思いを風に託すしかないという、切実な気持ちの表れでしょう。
ここには、冒頭の「みなまで言わないでくれ」との対比も見て取れます。
初めは「言葉を拒む」ことで悲しみを閉じ込めていた語り手が、最後には「届いてほしい」という願いに変わっていますね。
その変化は、まるで岩屋に閉じこもっていた“山椒魚”が、ついに眩しい外の世界へ目を向ける小さな救いでもあります。
風に灯る“あなた”という燈。喪失を受け入れた成長の痕跡

----------------
さよならも言えぬまま
一つ報せも残さずに
去り退いたあなたに
祈りを送りながら
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
ここで別れの言葉が出てきました。別れとは、時にこちらの準備とは無関係に、唐突に訪れるものです。
この一節では、「さよなら」すら交わすことができなかった別れの痛みと、その後に訪れた静かな祈りの感情が、凛とした言葉で綴られています。
何も告げずに去ってしまった「あなた」は、物理的な死を暗示しているとも、あるいは心の距離を意味する別れとも取れるでしょう。
どちらにしても、「報せも残さずに」いなくなってしまった相手に対し、語り手は怒りや恨みではなく、祈りを送る。
そこにあるのは、深い喪失感と、それでもなお想い続ける切実な優しさがうかがえます。
「祈り」という行為は、相手と直接つながることができなくなったときに、ただ静かに、しかし確かに“心を送り出す”ための手段です。
このフレーズは、目の前にもういない「あなた」に向けた最後の手紙のようでもあり、語り手の内なる和解や救いの兆しを感じさせるようにも思えます。
----------------
青く澄んでは日照りの中
遠く遠くに燈が灯る
それがなんだかあなたみたいで
心あるまま縷々語る
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
そんな別れを受け入れた後に描かれるのは、まぶしいほどの夏の光の中にぼんやりと灯る「遠くの“燈”」で、それをかつて共にいた「あなた」を思わせる存在として語られているのです。
続く「青く澄む」という言葉には、悲しみや喪失を超えた静けさと透明感が宿っています。
まるですべての感情を涙のように流し切ったあとの空のように、澄んだ心で、語り手は遠くの「燈」を見つめています。
そう「あなた」を見つめる理由は、きっとまだ、その光を大切に想っているからこそではないでしょうか。
そして最後に「心あるまま縷々語る」という言葉で締めくくられるのは、語り手が今もなお、その記憶を慈しみながら生きていることの表れです。
縷々とは「仔細を語る」という意味ですが、「細く長く」「途切れることない」という様子を想像させます。
つまり、断ち切るのではなく、絶え間なく“語り続ける”。
それは忘却ではなく、想い続けることの証であると考えます。
この終幕は、喪失や後悔に覆われた歌の中に、ほんの少しの温もりを残しているようです。
それは、岩屋の中でただ泣くだけだった山椒魚が、祈りと共に一歩前に進むような、静かな「再生の兆し」とも読めることでしょう。

----------------
今なお浮かぶこの思い出は
何処にも落とせはしないだろう
≪海と山椒魚 歌詞より抜粋≫
----------------
これまでに出てきた「今なお浮かぶその思い出は 何処かで落として消えるのか」からはトーンが大きく変わり、再び気持ちが語られます。
「“その”思い出」と「“この”思い出」では、距離がさらに近くなり、まるで自分の一部のような感覚であることが分かります。
そして、「何処かで落として消えるのか」と「何処にも落とせはしないだろう」という変化からは、思い出に対する思いが大きく異なります。
以前は、何処かで落としてしまう不安定さと、手放して楽になりたいという気持ちが感じられますが、今では思い出は決して消えることがないと断言しているようです。
ここには、かつては消えてほしかった感情を、今では「消せない」と受け入れ、そしてそれを大切に抱き続けていく覚悟のようなものがにじみ出ています。
この対比は、物語的な成長の痕跡とも読めますね。
つまり、歌の語り手は「喪失の痛みを消したい」と願っていた初期の段階から、「その痛みすらも、自分の一部として生きていく」という境地へと至っているように感じられます。
「忘れられない」ことは時に呪いであり、時に祈りであるという視点は、『海と山椒魚』という楽曲の構造にも、人の奥深くに棲む感情を書き続けた井伏作品の思想にも、美しく共通しているようです。
忘れられない記憶と共に生きることは「前進の証」

楽曲『海と山椒魚』は、他者との喪失に向き合いながらも、記憶を手放さずに生きる決意を描いた楽曲のように思います。
「消えてほしい」と願った痛みが、やがて「消せないもの」として受け入れられていく、その心の移ろいが、詩の中で丁寧に刻まれています。
楽曲のモチーフとして取り入れられた小説『山椒魚』は、孤独や閉塞感と向き合う語り手自身の姿でもあり、そこに宿る祈りは井伏作品の思想とも呼応します。
忘れられない思い出は、時に重荷になり、時に心を灯す光にもなる。
そんな感情の揺らぎを、米津玄師さんは本楽曲にて美しくすくい上げてくれました。