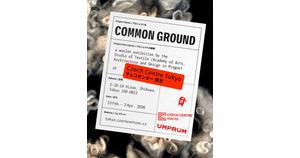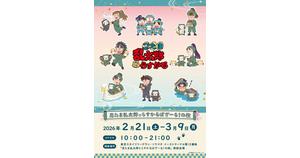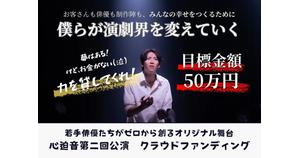TOP画像引用元 (Amazon)
迷いの中に確かに光る角松テク
こなれたバブリー感「to be or not to be」
典型的ディスコサウンド系イントロ。
このまま昭和と平成の輝けるポイント通過に突入するかと思いきや、続くトランペットの音は絶頂期のそれより、どこか抑制が効いている。
あの頃の、無理のある未完成にデコレートされた街並みではなく、再開発後の渋谷といった完璧な空気感が広がる。
これに逆行する「高校生の思い出」なる歌詞が凄い。
この革靴とスニーカーによる命がけの綱引きは、しぶとく、果てしなく綺麗な光景だけを見せる。
角松敏生の底力がダイレクトに出た作品だ。
脆さvs帝王のプライド「大人の定義」
フォークソングなギターのイントロに、血を吐くような角松の枯れた語り。
少年のころの疑問ではなく、今の"何もかも知り尽くした大人"になった率直な、人間の核のような思いがリスナーの脳に刻まれる。
半端ない束縛感に身動きとれないでいると、「分かるけど分からない・・・」の女性ボーカルのあと、突然ブラックミュージック的なテイストに転換する。
そして後半再び、心の語りに戻るのだが、そこに畳みかけるしつこさはない。
むしろメロディーのきめ細かさ、音作りの整然としたプロセスが、手にとるようにわかる仕上がりになっている。
聴くたびに唸ってしまう作品だ。
ありきたりの中に潜む非凡な才能 「恋ワズライ」
かつては、作品のサブタイトルに、自分が愛していた女性の名前をつけていた角松敏生が、このような純愛を呟いている。
にもかかわらず、職業的文学のあざとさがまったくないのは、リズムとメロディーとの隙間ない調和のせいだろう。
レゲエともいえない半端に変則的なバウンドに折り重なるように"歌"がなじむことで、転がりながら無理なく曲が進んでいく心地よさがある。
派手さはないが、"かけがえのない何か"のような作品だ。
角松敏生の秘めたる開花宣言!
裏のカオをもつ応援ソング 「東京少年少女」
陰鬱、深刻なノリから、急に舞台セットがひっくり返ったような陽気なサビ。
が、鋭角的なリズムの刻みが冴えているため、ミュージカル音楽のような膨張感はなく、無駄のないいい女的サウンドに仕上がっている。
この曲のテーマは少年少女への応援、励まし。
しかしあまりにも文句なしのハッピーエンド感は逆に、角松敏生の現役への意欲を感じさせる。
テクニック面では大御所であることを証明しながらも、ミュージックシーンから離れた場所で、晩酌に「あ゛ー」と汚い溜息をつく爺さんになるのは御免だと言っている。
角松敏生の明るい未練がにじみ出た作品だ。
ヴィジュアル系、ヒップホップ・・・ 多様化し、複雑化するミュージックシーンは角松敏生の心をかなり疲弊させたことは否めない。
しかし、彼が今も当たり前の綺麗な仕事をしていることがわかってほっとした気分だ。
角松敏生にはしばらく"頑張れ"という言葉は不要だ。
TEXT 平田悦子