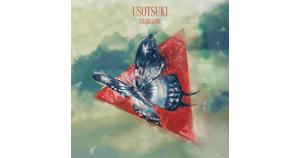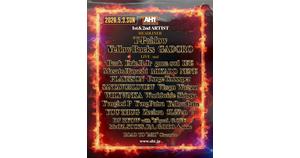『ホテル・カリフォルニア』における三幕構成

映画における三幕構成とは、第一幕が「発端(出会い)」、第二幕が「発展(対立)」、第三幕は「結末(解決)」といわれており、またその配分はだいたい1:2:1が最適といわれています。
そのように『ホテル・カリフォルニア』を区分していきますと、以下のような具合になります。
●第一幕(出会い)
砂漠を走っていたがほとほと疲れたので、灯りを頼りにホテル・カリフォルニアを訪れる。女が道案内してくれるので良いところかなと思う反面、なんとなく気味悪いところだなあと思いつつチェックイン。(ここまで一番)
●第二幕(対立)
女は妙に派手だし男侍らせて踊りまくってるし、ワインくれっていってんのに1969年のスピリッツはないとかいうし、なんかヘン。(ここまで二番)あげくに女が「わたしたちは囚人なのよ」なんていい出す始末。ははあ、これはおおよそ見当ついてきたぞ。うわ、みんなあつまって生き物をナイフで殺そうとしてるし、これはまじやばい!
●第三幕(解決)
まじやばいここ!逃げなきゃ!必死の思いで出口を見つけるも、守衛が彼を制止します。「ホテル・カリフォルニアはいつでもウェルカム。でも出られないんですよー、ごめんねー。」
「コリタス」とサビにおける映画的効果

さて、この曲は発表以来さまざまなバリエーションの解釈を生み出し続けています。
字数の制限上例を挙げるのは避けますが、さまざまな見方をされてしまうのは、意味深長なワードが数多く見られるからです。例えば一番の冒頭、
--------------------------------
Warm smell of colitas - rising up
through the air
≪Hotel California 歌詞より抜粋≫
----------------
[日本語訳]
温かいコリタスの香りが、あたりに立ち込める
---------------
というセンテンスの中の「コリタス」というワード。
やれ大麻のスラングだとか、いやこれはヒスパニックでいうところの「けつっぺた」だとかいろいろいわれておりますが、調べてみますとどうやら本国のアメリカ人でも「コリタス?はあ?」という言葉らしいのです。
だとすれば、アメリカ人でもわからない言葉をあえて使う意図とは何なのか。
そもそも通じない言葉が正しく理解されると誰が思うでしょうか。通じない言葉はただの響きでしかありません。つまり重要なのは、その言葉の響き。そこからリスナーが想起する感覚、さらに不吉な予感へと導くことだったのではないかと考えます。
「暗い砂漠のハイウェイのコリタス? よくわからんがメキシカンな響きだぜ、なんか国境あたりのやばい香りがする言葉だぜ…」
――と感じさせることで、
「そんなやばそうな匂いが立ち込めているとなると、こりゃおかしなことが起こりそうだぜ…」
――といったような、不吉な予感にリスナーを導きたかったのではないでしょうか。
いうなればコリタスとは、物語を誘導するための仕掛けに過ぎない、それそのものは置き換え可能な言葉。ちなみに映画ではこうしたアイテムを「マクガフィン」といい、しばしば用いられます。
もちろん言葉のアートである詩に対して、言葉はなんでも置き換え可能なんていうのは無粋な話。しかしドン・ヘンリー自身は、この『ホテル・カリフォルニア』の意味することについて、
"a journey from innocence to experience, that's all."
「ねんねから訳知りへの旅、それだけさ 」
と投げやりに語っていますので、あまり言葉ひとつひとつをとらえて深読みするのもどうかと思うのです。
もう一つだけ映画的手法としてみる例を挙げます。「反復」という手法です。映画では、同じようなシーンを反復することでテーマを強調する、という技法がしばしば使われます。
この曲で反復といえばサビ。サビなので当たり前ですが「Welcome to The Hotel California...」の部分は二回繰り返されています。
一回目のサビは、「出会い」である一番の歌詞を受けたものでしかありません。しかし二回目のサビは「出会い」と「対立」の場面まで受けているので、同じような内容であっても少し違ったイメージを抱かせます。
このイメージの差分によって「どうやらホテル・カリフォルニアという場所はやばいかもしれない」という印象を強めている、と見ることもできます。
映画のように楽しむ『ホテル・カリフォルニア』

映画のなかで意味深長なオブジェを置いたり反復するシーンなどを描くのは、それそのものの意味するところを知ってほしいからではありません。
そこで沸き起こる感情を利用して、意図するところに誘導するのが目的なのです。
この曲を映画的な構造に当てはめてみると、一見謎めいたワードや情景も実は『ホテル・カリフォルニア』の象徴性やその正体に導くための仕掛けに過ぎないのではないかと思えてきます。
少なくとも「精神病院のことを歌ってる」というような突飛な発想に至ることなく、テーマの核心に迫れそうな気がしてなりません。
このように捉え直し始めると、問題の「1969年以降のスピリッツは置いてません」のくだりもまた違った味わいが感じられますが、このあたりはまたの機会にするといたします。
TEXT quenjiro