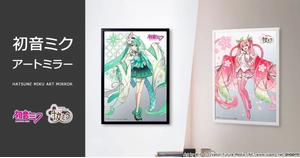ライブ前後のお客さんの肉声はレア
──9月28日に「The Documentary of SUPER BEAVER 『東京』Release Tour 2022~東京ラクダストーリー~」がリリースされます。なぜドキュメンタリー作品を制作することになったのでしょうか?
上杉研太:これは自分たちが発信というよりも、メンバーの近いところにいる人たちから“録りたい”という意見が上がってきたんです。少し前にテレビで1年密着取材していただいて、そういったチームとすごくグルーヴも生まれていて、「また一緒にやりたいね」と言ったことも、ひとつつながったことでもあって。そこからこのホールツアーに対して、「今一度ドキュメントという形で、つねにカメラを回して、SUPER BEAVERのオンステージしてないところの、バンドのありのままの姿を映した作品にしたい」というお話をいただいたので。
そういう声が上がってくるということは、ここまで続けてきていて今、そういったところにフォーカスを当てても、何か感じてもらえるような状態にバンドがあるのかな、とも思いましたし。いろいろなことが重なって、こういう感じになったんですよね。
──今回のホールツアーは“あなたのふるさとに会いにいく“というコンセプトもあったと。
渋谷龍太:この『東京』(2022年2月23日リリース)というアルバム、『東京』という曲もそうですけれど、ことさら“東京”にフォーカスした曲ではなくて。それはどこなのかというと、郷土的なものだと思うんですよね。自分が生まれた場所に限らず、自分が気持ちの軸足を置く場所だったり、土地であったりとか、そういうものに思いをはせていただけると、すごくグッとくるアルバムができたのかな、と思っていて。ホールというのはどの会場に比べても、その街の空気感や景色を、一番濃く反映される場所で。ライブハウス、アリーナでできないことをホールという箱はやっている場所だと思っているんです。
ライブハウスは意外とどの土地にでもあったりするんですけれど、あれは一つの文化であり、サブカルチャーだと思っているので。アリーナというのは大都市にしかなかったりして、どちらかと言うと足を運ぶ場所というイメージがあると思うのですが、ホールというのは、結構どの市にもあって。いろいろなものに使えて、足を運びやすい。そうすると、おのずと来て下さる年齢層も広がるので、限りなく街の空気に近くなるんですよね。だからこのアルバムとホールの相性はすごくいいし、親和性は強いんじゃないかな、と思っています。
──確かに各都市のホールというと、地元の市のオーケストラ演奏会とか、講演会をやるとか、目的は多種多様ですね。

渋谷龍太:おじいさん、おばあさんがたくさん来る日もあるし、それこそ子どもの発表会を親御さんが見に行くような機会もある中で、ホールにしてみればバンドの演奏というのは、どちらかというとイレギュラーの方になるんじゃないのかな、と。
皆さんのなじみのあるところとなると、自分の子どもを連れてこようと思う親御さんもいらっしゃると思いますし、逆に自分の親御さんを連れてきたいと思う子もいるかもしれない。すごくハードルが下がるというか、敷居が低めになると思うんです。それに対しては、自分たちの音楽と自分たちが向けている年齢層や幅の広さも、すごく近しいものがあって、SUPER BEAVERとホールというのは、意外と相性が良いと勝手に思っています(笑)。
──今回、お客さんのコメントもたくさん収録されています。
柳沢亮太:今回のドキュメンタリーという作品の特性で言うと、いつもはBEAVERのライブを見に来てくださっている方、もしくは家で音源を聴いていただいている方も、普段はなかなか目にしない部分がすごく収められているものだと思うんです。また僕らも見に来てくださっている方の生の声、しかも見ている最中ではなく、その会場に到着した瞬間や帰る間際の肉声を聞かせてもらう機会は、実はほとんどないんですよね。だから僕らすごく新鮮な映像というか。見に来てくださっている方にカメラを向けてお言葉を直接聞いて、僕らのところまで届けていただくということはやはりないので、それはすごくうれしいなと、純粋に思いました。
ああいうインタビューの一つひとつにしても、普段はステージとフロアで気持ちが行き交う、というところだけですけれど、そこからまた一つ離れて、それぞれどういう気持ちがあって、どういう関係性でここに足を運んでくれてるか、みたいなことまで、少し垣間見えるので。それは自分たちにとってもすごく新鮮な部分がありました。
最初からディレクターさんは「」それぞれの街であり人をやはり録りたい」とおっしゃってくださっていたんです。そういった部分を収めていただけたと思います。
──今作品は、お客さんが主役になっている側面もある、と感じました。

藤原”34才”広明:さっきも言っていた終わった後の話もそうですけど、一本一本やるたびに、その場で録ったものを見たかったなって(笑)。単純に喜んでもらいたいし、さっき言っていた家族が集まるきっかけというのもそうですけれど、そういうのを見ていると、当たり前ですけれど僕らも「また来たい」と思うし、バンド長く続けて、また再会してほしいな、と思うし。何より“やっていて良かったな”という、やりがいみたいなところにすごくつながっているので。うれしかったですね。
──どの年代のお客さんも、SUPER BEAVERに対してたくさん語りたい、という気持ちがあふれていました。
渋谷龍太:なんでもきっかけになれたらいいな、と思っていて。久しぶりに集まろうとか、大事な家族と何かを話そうって思った時の議題に上がることって、絶対に楽しいことであるはずだし、それは結構、限定的だと思うんです。そして、そのきっかけになれることは、すごく重要な部分だと思っていて。“ライブに行くから集まろうよ”とか、ライブに行くから“親を誘ってみるか”とか、“うちの子を連れて行こうかな”もそうなんですけれど、それはすごくレジャー的なもので、そういった共通してワクワクできることしか、人と一緒に共有したい、と思わないはずだと思っていて。その一つになれると言うのは、誰しもができることではないと思うから、やはりとても光栄だな、と思います。たかが音楽だからこそ、そこにまで踏み込めるというのは、とても尊いですよね。
──SNSといったように個人で楽しむことが増え、隣の人が何を楽しんでいるのか分からないということも多い中で、これだけ、親にも話せる、自分の子どもにも話せるという、1つのコンテンツになるというのはすごいことですよね。コンテンツという表現ではないかもしれないですが。
渋谷龍太:いや、全然それはいいと思いますよ。そのことに対して「ねえ、聞いてよ」と言えて、受けとった人も「ああ、そうだったんだね」と返すことができる、本当に1コンテンツだとは思うんです。ただインスタント的な、使い捨てのものでもない。ずっと続いていく、脈々とつながっていくものになると、何年経ってもその話題でお話ができるとか。そういうもの一つにはなりたいね、というのはすごく思っていましたから。
スタッフの熱量は自分たち次第
──もう1つ、今回のドキュメンタリーでフォーカスされていたのが、スタッフの皆さんです。
柳沢亮太:やはりライブひとつとっても、もちろん4人だけで全てができるわけではないので。ツアーおよびバンド・ライブというものが、いかに一つの楽しいを作るために、どれだけの人が関わってくださっているのかというところは、より伝わるでしょうし。
それは逐一お伝えすべきことなのかどうなのかは、分からないんですけれど。基本的には、自分たちのオンステージで託されている部分がすべてだと思うので。“実際はこうやって動いているんだよ”ということを教えたいわけではないんですけれど、そういったところも入ることによって、このライブであったり言葉だったり音楽だったりが、より立体的になっていく感じはあるのかな、と思いました。
──広島公演では藤原さんの「俺ら広島Cave-Beで、ガラガラでずっとやっていたんだから」、「やろっか」という一言によってスタッフさんがライブ中に急遽、「広島Cave-Be年内押さえました」というサプライズがあって。藤原さんが「スタッフが仕事できすぎるから(笑)」と言っていましたよね。
藤原“34才”広明:本当に早かったよね。
柳沢亮太:あれはマジで、自分でも想像しなかった一つではありましたね(笑)。
渋谷龍太:普通では考えられない迅速な動きだから、たとえ業界のことを知らない人でも、「いや、この早さはさすがに無理でしょう」と思ってしまうかな、と。しかもあまりにも迅速にポスターまで作ってもらって。
柳沢亮太:逆にペラ一枚で雑に見せるなんていう、謎の行為が起きるくらいで(笑)。実はちゃんとデザインして、プリントアウトまでしてくれていたんです。
──え、そうだったんですか!?

渋谷龍太:すぐプリントしてくれて、「これを貼ります」と言ってくれたんですけれど、「いや、ちょっと待って」となって。
柳沢亮太:「逆に文字情報だけのものに変えよう」と、退化させたという(笑)。そんなことが起きるくらい早かったですね。
藤原”34才”広明:それくらいスタッフが優秀だったという。
──映像で映っていた手書きが最終形だと思っていました。
藤原”34才”広明:そんなことないんですよ。完璧すぎて。
──何回もその地に足を運んで、スタッフさんたちと絆を深めていったからこそできた、という一つの例ですよね。
上杉研太:それは本当にもっとも重要なことだとは思っていまして。こっちはこっち、そっちはそっち、と分かれていたら、たぶん辿り着けないステージというのは絶対あって。自分たちが最高のライブができたという時に、同じ熱量で喜び合えるチームが作り出せるものと、「あ、お連れ様でした」ぐらいの関係性のスタッフさんとやるというのと、まったく違っていて。
もちろんそれは仕事として間違っているわけではないから、逆に自分たち次第だな、というか。自分たちがその懐まで入り込んで、お互い一緒に「いいものを作ろう」という空気感でバンドが動いてるかどうか。「こいつらのために頑張って、いつもより1時間早く入りして、最終調整しよう」とか、そういうところのレベルまで食い込めるかどうかは、自分たち次第だと思うんです。
初日からファイナルに向かって行く時には、細かくディスカッションしたり、お互い反省会をしたりして。結果、最終的にチームが一丸となるところに行くのかなと思っています。
──ステージの解体作業に入っている方々に挨拶したり、働く人間としての視点からも、メンバー皆さんの日常の行動から、「こういうふうに人と接したい」などと、いろいろ感じるものがありました。

柳沢亮太:バンドマンがどうとかということ以前に、人と人のつながりというか、向き合い方みたいなものを基本的にすごく大事にしているバンド、メンバーだと思っていますし。ことさらバンド、チームということだけに着目してみると、やっぱり互いの心遣いというのは、すごく重要なことだと思いますし、その心遣いがあってしかるべきだと思うんですけれど。変な気の遣い合いというのは、チームとして僕はあまりない方がいいな、と思っていて。
“こうしたらもっと良くなるんじゃないか”とか、“あそこは良くなかったんじゃないか”とか。そういったところは、携わってくださったチームとも、もちろんスタッフ同士でも、スタッフとメンバーもですけど、やっぱりできる限りフラットにというか、会話ができるチームでありたいな、というのが、今回に限らず、ずっと思うことではあるので。そういう部分というのは、もしかしたしたら、今回、映り込んでいるのかもしれないですし。
でも別に無理にもめたいわけではないですよ。必要ない言葉をかけあうことはないのですが、ちょっとしたコミュニケーションも含めた上での会話は多い方がいいな、と思っています。
さらに強くなれる余白が残っている
──ドキュメンタリーの後半では予想外のことが起こって、そこでメンバーの皆さんの緊張感、責任感といったものがダイレクトに伝わってきました。
藤原”34才”広明:ああいうことは、本気でやっているから起こるんですよね。メンバーだったからそれが目立ったことになりましたけど、PAさんの音が出なかったとか、照明さんが間違ったところで明るくしちゃったとか、そういうこともありえるし。そういった時「音、出なかったですね。次、頑張りましょう」というよりかは、「駄目ですよ」という話を普通にするのと一緒で。それを僕らも何かミスしてしまったら、スタッフさんに「申し訳ないです、あの時、キック一発踏めなかったです」とか、日常的にやっていることなので。
けれどみんなでさらに話すことができて、ここからまた一致団結して頑張るぞ、と再決起できたので。単純にツアーを全部やりきれたことはすごくうれしいし、こんなご時世でツアーが飛ばすにできたというのも、ありがたいことですから。まだまだ強くなれる余白があるというか。完璧なショーをやったつもりだけど、もっといいショーができる未来があると感じられて。だから、まだまだ強くなっている途中だと思います。
上杉研太:それを踏まえて生まれたものとか、「よっしゃ、頑張ろう!」とまたなれたことの方が、バンドとしては、とてもいいことだと思いますね。
何が大事なのかといったら、やっぱり本気でやることであって。人だからミスすることもあるけれど、最終的には、そこでどうしようかとか、これを踏まえてどうしていこうか、ということが話せたなら、それはマイナスではなくて。その時の突発的なものに対してわきあがってくる感情はありましたけれども、とてもいいファイナルだったんじゃないかな、と感じています。
──上杉さんは“年齢を重ねる中で、ちゃんと変わっていかないといけない。その変化に自分が気づいて、その変化の中で変わらないものって何だろうと、確かめ合うことができている”とお話されていて、それも継続されているバンドだからこその言葉だと思って、印象に残りました。

上杉研太:個人的にもバンド的にも、この年齢だからこそたどり着ける楽しさや幸せがある一方で、“嫌だな”と思うこととか、“これは違う。これは許せない”という感情というのも、年を取っていくごとにアップデートされていくものなのかな、と思っていて。そういうものが反映され続けていくことは、ことさらこういうバンドだったら必要なのかな、と感じています。
だからいつだって等身大なんですけど、ただ“今の等身大は何だろうな?”ということを、自分だけじゃなくて、バンドとしてなんだろうな?というのと、逆に自分やバンドを注目してくれる方が、どういうようなことを求めているんだろう?というような、いろいろな角度から考えたいな、と思っています。
──普段は目にすることのできないライブの裏側や皆さんの姿を見ることができ、音源やライブ映像作品とはまた違った形でSUPER BEAVERの底力といったものを感じました。
渋谷さんは前回のインタビューで、“その人のことがより分かるからドキュメンタリー的なもの見るのは好きだけれど、自分が密着映像を撮られるのは、正直、あまり好きではない”とおっしゃっていましたが、今回、1つの作品になってみていかがでしたか?
渋谷龍太:この作品は僕たちが見せるべきところではないところにフォーカスが当たっているから、これがいいものなのかどうなのかというのは、自分ではなかなか判断しづらいところではあります。今までの作品とは違い、自分たち発信からきたわけではないので。
でも、探りたい人が探れる一つのアイテムとしてあったらいいな、と思います。たとえば“こういう工程を踏んでいるから、このご飯はおいしい”とか、別に知らなくてもいいことではあると思うんですよね。でも“なんでこんなおいしいんだろう?”と思った時に、“ああ、このことか”と分かる。これはそういう作品になっているから、手を伸ばしたいものであるならば、見て欲しいなと思います。

TEXTキャベトンコ
PHOTO Kei Sakuhara
SUPER BEAVER(スーパービーバー)。 渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(G)、上杉研太(B)、藤原“35才”広明(Dr)の4人によって2005年に東京で結成された。 2009年6月にEPICレコードジャパンよりシングル「深呼吸」でメジャーデビュー。 2011年に活動の場をメジャーからインディーズへと移し、···