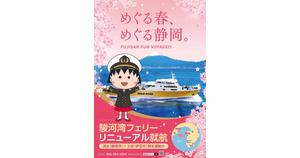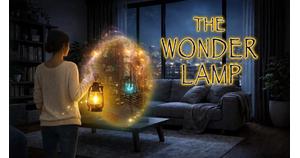『通りゃんせ』に漂う不気味なイメージ

『通りゃんせ』という童謡をご存じでしょうか。
江戸時代に成立したといわれる古いわらべ歌ながら、子供たちの遊びになっていたり、横断歩道のメロディに使われていたりと、どこかで耳にした経験のある人は多いのではないでしょうか。
遊び歌として知られ、「親」になった子供が二人で手を繋いで橋を作り、そこを「子」役の子供たちがくぐるという遊びです。
歌を歌いながら順番に橋の下をくぐり、歌が終わった瞬間に「親」が降ろした腕の中にいる子供が捕まるというもの。
小さい頃に友達と遊んだという人もいるでしょう。
非常にポピュラーなわらべ歌である『通りゃんせ』ですが、意味深な歌詞のせいか、怖いというイメージもあります。
では、なぜ『通りゃんせ』の歌詞が怖がられるのか、その理由を考察していきましょう。
特別な許しを得て参る「てんじんさま」

----------------
とおりゃんせとおりゃんせ
ここはどこのほそみちじゃ
てんじんさまのほそみちじゃ
ちっととおして くだしゃんせ
ごようのないものとおしゃせぬ
≪とおりゃんせ 歌詞より抜粋≫
----------------
「とおりゃんせ」は「通りなさい」という意味の言葉です。
どうやら、子供が七歳になったお礼参りに来た母子を歌っているようですね。
『通りゃんせ』発祥の地といわれる場所はいくつか候補があり、神奈川県にある山角天神社や菅原神社、または埼玉県川越市にある三芳野神社の名前が挙げられています。
山角天神社は学問の神様として知られる菅原道真を祀っている場所で、地元の人からは「天神さん」と呼ばれて親しまれているそうです。
歌詞にもある通り、まさに「てんじんさまのほそみち」を辿っていく神社です。
細道を歩いていく様を想像すると、厳かな気持ちになりますね。
----------------
いきはよいよい かえりはこわい
こわいながらも
とおりゃんせとおりゃんせ
≪とおりゃんせ 歌詞より抜粋≫
----------------
また、菅原神社を舞台にしているという説では、お参りのために箱の根の山を越えて訪れるも、帰る頃には関が閉まってしまうため、「いきはよいよい かえりはこわい」という歌詞に合致します。
最後に、川越の三芳野神社は、川越城の場内に位置していたため、参拝するには許可が必要でした。
神社のすぐそばに川越城本丸御殿があるのですが、警戒態勢が敷かれるのも納得です。
また、参拝後も厳しいチェックをくぐり抜けなくては帰ることができなかったため、やはり「いきはよいよい かえりはこわい」とリンクするのです。
また、三芳野神社では三芳野神社大祭と七五三のお祝いの時のみ、特別に一般人の参拝が許されていたそうです。
『通りゃんせ』の歌詞に登場する「このこのななつのおいわい」は、それほど特別な事情であることが分かりますね。
子供の健やかな成長への感謝を込めて、特別な許しを得てお宮参りをするのだとしたら、『通りゃんせ』という曲に漂う厳かで重たい空気感も理解できます。
「いきはよいよいかえりはこわい」に込められた意味

『通りゃんせ』で歌われている「いきはよいよい かえりはこわい」という歌詞は、帰り道の厳しいチェックを意味しているという説がありますが、実は他の説も存在します。
また、この歌詞のイメージから『通りゃんせ』にはどこか不気味なイメージがついているように思えます。
行きはよくて帰りがこわい(怖い)理由の一つが口減らし説。
口減らしとは、作物の不作や干ばつなどによって生活が苦しくなった際、子供をあやめたり身売りしたりすることです。
そして、口減らしの一つとして『通りゃんせ』でお参りする神社で、子供に手を掛けていた説があるようです。
子供は七つまでは神の子といわれ、まだ人間ではありません。
神の子である子供を、人間である自分の手元から神様へお返しするという理由で口減らしが行われていたとする説です。
自分の子供に手を掛けるとは信じがたいかもしれませんが、冬至の暮らしは今ほど豊かではなく、貧しい家では大人が生きていくだけで精一杯であったと考えられます。
とすると、自らの手で子供を神様の元へ返そうとする親がいても不思議ではありません。
また、歌詞に出てくる「こわい」は「怖い」という意味ではないという説もあります。
「こわい」という方言には、だるいや疲れたという意味があるらしく、『通りゃんせ』に出てくる「こわい」も同様の意味ではないかとする説です。
『通りゃんせ』は古い歌なので、今のように交通手段が発達していない時代に地方から天神参りをしたのだとしたら、行きは頑張れても帰りは疲れ果ててしまいますよね。
遠出する時、ましてや小さな子供を連れていれば、行きこそよいものの帰りは大変でしょう。
そのような心情を歌ったのだと考えると、『通りゃんせ』に漂う怖いイメージも払拭できそうですね。
『通りゃんせ』の歌詞に見る当時の人々の生き様
このように、『通りゃんせ』が怖いといわれている理由を探っていくと様々な解釈に辿り着きます。歌詞も非常に短く単純で、細かい描写がないため、どの部分に着目するかによって様々な解釈ができることが魅力ですね。
確かなことは分かりませんが、歌詞を深掘りしていくと江戸を生きた人たちの日常や心意気が分かり、面白いかもしれません。
童謡は子供の歌というだけでなく、当時の暮らしを知る貴重な資料にもなります。
わらべ歌として慣れ親しんだ『通りゃんせ』から、当時の人々の暮らしぶりや生き様に思いを馳せてみるのも面白いのではないでしょうか。