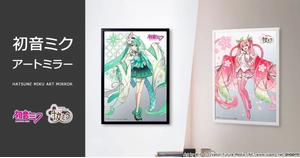まず隣の人のことを考えて歌いたい
──ニューシングル『ひたむき』の表題曲は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のオープニングテーマソングですが、SUPER BEAVERそのものが表れている曲になっていますね。
柳沢亮太:すごくSUPER BEAVERらしいというか。これまでもそういう楽曲はいっぱいあると思うんですけれど、「SUPER BEAVERってどんなバンドですか?」と聞かれた時に、自分たちでも「ひたむきなバンドだよね」と、どこか思えるような、それぐらい親和性の高い言葉だと思うので。僕らのあゆみを表した1曲でもあると思いますし、あゆみに対するスタンスというか、大事にし続けている気持ちや思いみたいなところが、分かりやすく楽曲になった1曲かな、と思います。
もちろんこういったお話をちょうだいして、作品とリンクする点は考えつつも、SUPER BEAVERがずっと大事にしていることが、今一度『ひたむき』というタイトルになってから、さらにより一層強固になって。今のSUPER BEAVERが歌い表すなら、というところを1番大事にして作っていきました。
──すでに主題歌として流れていますが、どんな感想が寄せられていますか?
上杉研太:「これってBEAVERだよね」という世界観の歌詞ですけれど、ヒロアカのヒューマンなストーリーにもはまっていて、「すごく興奮した」と連絡をくれる友だちもいましたね。
──歌詞については、最初と最後が<自分は自分だからってのはさ 言い訳の そのための 決意じゃなかったろう>と、同じ言葉が置かれています。曲を通して聴いていくと、最初は問いかけで、最後はアンサーになっているような気がしたのですが。
柳沢亮太:頭の2行と最後の2行は、まったく同じ言葉ではあるんですけれども、受け取り方が、曲を通して聴いていくことによって変化するというのが、この曲の特徴というか。でき上がって改めて聴いてみると、投げかけるというよりは、自分自身との対話ともとれる楽曲なのかな、と思います。この冒頭2行と最後の2行も、それぞれのアンサーというか捉え方で、少し響きが変わる、意味が変わるような構成になっているな、と思いますね。
──そして<どれだけ愛を謳っても 悪意は未だ消え去っていない>という歌詞のところは、非常に考えさせられるフレーズでした。

渋谷龍太:自分は“悪意が消え去るだろう”と思って歌を歌ったことがないので。音楽に対して世界平和とか思ったことはあまりないんですよ。そういうのって、いくつも先の話だと思うから。もっと個人単位のことを考えるのが先なんじゃない?と思うんです。広い枠組みでとらえるから難しくなるのであって、ただ単純に隣の人のことを考えて歌を歌えばいいんじゃないかと思っていて。
何かを照らし合わせる対象の時に、人生という大きいくくりでもいいけれど、来週とか、明日とか、もう少し分かりやすい、自分がとらえられる範囲の基準で物事を考える方が僕はいいな、と思っているので。だからとりあえず自分の手が届く、目が届く範囲を、とにかく大事にすることに力を注ぎたいと思っています。それが個人単位に広がれば、大きな話になるのであって。だからあきらめとか諦念の感じで歌っているわけではないんです。ある程度、それはそうだって思っているからこそ、という解釈ですね。
──伝わってくるテーマは大きいけれど、それは個人の身近なことが積み上がった結果である、と。
渋谷龍太:この曲はわりとSUPER BEAVERの歌の中では、かなり個人にフォーカスしていると思うので。ひいてみた時には大きな話だし、全体の話ではあると思うんですけれども、最初に考えるべくは、外見よりももっと核心の部分であったり、大きなくくりでも個の集合という。個の部分にまず目を向けるべく、そういう歌だと思います。
柳沢亮太:言葉に関しては最初に言った、わりと自分と問いかけ合うというか。自分がこれからの人生において選択していく中で、正解というものはおそらくないでしょうし、自分が正解だと思うことが、誰かにとっての最悪かもしれない。
それは今回のテレビアニメの中でも同じで、一見、悪だとされているものたちにも、そうなってしまった動機と理由がある。もちろん一方から見ればそれは敵なんだけれど、どうしても敵と言い切れない、一縷の白の部分があって。一方が完全に悪であることは、なかなかない。ということを考えると、聴いてくださった時に、“でもこれは、分からないな”という部分ももちろんあるでしょうし、“うわ。分かっているけれど、そこまで言われると”と思う部分があるかもしれない。
だから一概にも言い難いなというところを、“それでもやめたくない。諦めたくない。まだ頑張りたいと思う”という、その道中のさまこそが、ひたむきさというのかなと思うので。あらゆる凸凹さだったり、いびつさみたいなものが、それすなわち「ひたむき」という。
そもそも答えを出したいという曲ではなかったんだと思います。自分の一番奥底で「こうやりたい」と叫んでいるその思いは、決して他者が聞ける声ではないと思うので。最終的には自分の中だけでわきあがってくる気持ちであり、それってすごく素敵な感情なんじゃないか、というところを、最終的には少し後押しできたら、という気持ちがありつつ作った曲ですね。
サウンドは鋭角で凸凹している
──この曲の特徴として、冒頭のギターのリフが、まず耳に飛び込んできますね。柳沢亮太:SUPER BEAVERはもともとリフ曲があまり多くはないので、かっこいいものが思いつけば、そういうのはすごく、1つの楽曲のモチーフになると思いますし。今回は、たまたまはまったというか。やはりキャッチーな何かがあることは、SUPER BEAVERにおいても非常にいいことだと思うので。それが今回、ギターであったんですけれど。ただあのイントロから始まるのは、この楽曲を象徴する1つのモチーフではあると思います。
──確かに1つの軸になっています。
柳沢亮太:序盤はあれがずっとリフレインして、ベースが音階を作ってくれて。
上杉研太:サウンド的にエッジが効いている楽曲だな、と思ったので。普通にギターがリフで行ったらベースはああいうふうになるな、と思ってやっているのですが、ちょっと面白いこともしていて。
やなぎが「やってみて」と言ったんですけれど、すごく歪ませたミュートという形で、ズンズンやるといった、普通ではやらないようなことをギターの後ろでやって、広げていて。そこからAメロに入った時にいろいろ展開していっています。総じてサウンド自体が鋭角で、ちゃんと凸凹しているというか。そこの出し引きがあるような感じが、トータルとしても特徴的だと思います。
柳沢亮太:そういう奏法にすると、やはり音色が変わるので。それは純粋に音符を短くして、音が鳴っている時間を短くタイトにしていくことによって、隙間がうまっていく。ドーンという音がドッドッと鳴るか、ということの違いなんですけれど、そういう奏法でやった時に隙間が生まれるところが、SUPER BEAVERではあまりやったことのないサウンドの作り方ではあったので。
実際にはまるかどうかは分からないけれど、ちょっと試してみたいということでやってみたら、僕らの今まで作ってきたものでは味わったことのない音像が上がってきて。そういう面白いと思うアイデアは、ふんだんに盛り込んでいきました。
──凸凹したサウンドというのも、この曲の特色なんですね。

上杉研太:ちゃんと一つひとつにスポットライトが当たっているんだけど、全体的に見るとすごく絶妙なバランスで、大きな塊になっているような。今までは全体で1つのスポットライトが当たっているようなサウンドもあったんですけれど、ギター、ドラム、ベースをそれぞれ聴こうと思ったら、全部それだけで単体で聴こえてくるような感じになっていると思います。
1つ1つがはっきり聴こえるということは、それだけシビアというか、繊細になってくるので、間であったりとか、誰かがいなくなった瞬間も分かりやすい。ゆえに、そういう表現もできる、という感じではあると思いますね。
──以前のインタビューでライブをやるごとに、演奏に対する意識がより高まっているというお話を伺いましたが、今回の曲もそれがふんだんに詰め込まれている、と。
上杉研太:そうですね。全部、地続きにはなっていて。いざ新曲をレコーディングするとなると、ライブで見つけたものであったりとか、アルバムを作って経験してきたものなどは、絶対に頭には入っていると思いますね。

藤原”34才”広明:今回はデモの段階からやなぎ(柳沢)はずっと「ドラムがバタバタいろいろなことをやって、最後までずっとやっていることが変わっていく、みたいなイメージだったので、そういう楽曲がまだあまりないから、SUPER BEAVERであってもよくないか?」と言っていて。
そういう発想からアレンジしていったので、できるだけブロックごとで違うことやっていこうというのは、最初から共通で決めていたというか。ドラムはずっと何かやっているのですが、それでもしっかり曲として成立させるために、超グッドメロディというのはもちろんですけれど、あとはギターとベースで、全箇所そのバランスをすごく綿密に組んだ感じはありますね。
柳沢亮太:アレンジに関しては、『東京』というアルバムのツアーだったから、地続きで繋がってるところはあると思いますし、そういったところでまたもう1段階ブラッシュアップできた音作りをして。ライブにおいてもそうなんですけれど、まず楽器陣の3人のアンサンブルが、「こういうふうにしたら、より歌が聴こえやすんじゃないか」という音づくりをして、そのままレコーディングスタジオにもフィードバックされて。
レコーディングで得た知識や経験を、またライブ会場に生かすといったことを繰り返していき、「音をいっぱい重ねなくても、一つ一つ存在感のある音でいたら、無理に重ねる必要はないな」という発想に至ったりしたんです。
だから<自分なんてとか どうとか>というところは、ドラムのリズムとベースと歌、後はクラップだけでも、十分こういう空気も作れるんじゃないか、と考えて。すべてが地続きになっていると思います。
──あと<自分なんてとか どうとか>のパートの最後で<でも悔やんでしまうんだよ 迷いながらじゃ結局>の<結局>が低くなってつながっていくところも、印象に残っています。

柳沢亮太:もともとデモを作った時は、下に転調していなくて。ただ最後のサビをもう1爆発させたいなと思った時に、いつもだったらさらに上乗せするんですけれど、発想を変えれば、手前が下がれば、また元に戻ったとしても上がるという印象になるので。これは単純な音楽的な発想ではありますね。
──歌に関してはいかがでしたか?
渋谷龍太:落とし込みたい部分は、すべてちゃんと落とし込めたような気がしますけれど、難しい歌だな、と感じています。構成的にも簡単な歌ではないから、カラオケで歌った人は大変なんだろうな、と思ったりします。
──歌うには、難しい曲なんですね。
渋谷龍太:センテンスで切り取るとそんなことはないと思うんですけれど、大枠でくくると難しいと思うんです。
──センテンスで切り取るとは?
渋谷龍太:難解なメロではないんです。わりとキャッチーなメロディが多いと思うから、その部分だけ歌おうと思えば、すっと歌える。でも乱高下が激しいし、それをひとつにつなげてみようとする時が、たぶん難しいんだと思います。
バンドの姿勢が表れたAcoustic ver.
──またこのシングルでは『秘密-Acoustic ver.-』が収録されていますが、アコースティックバージョンとして今回、『秘密』(2016年6月リリース5thアルバム『27』収録曲)を入れようと思われたのはなぜでしょうか?
上杉研太:『秘密』はコールアンドレスポンスを大事にしながらライブでやっていた曲だったので、コロナになってからあまりやらなかった曲だったんです。でも今年のホールツアーでは結構やることになって。
シングルでタイアップをいただいてドーンとやる時に、今の自分たちのライブでのスタンスというか、「今、こういうふうに動いている」という姿勢のようなものを『秘密』を入れることで、またパッケージできるんじゃないかな、と。来年アコースティックツアーもやるので、アコースティックの楽曲をバンドとしても、そういうアプローチを増やしていってもいいと思うし、元来アコースティックがとても合うバンドでもあるので、「何の曲をやろうか?」となった時に、『秘密』がいいいんじゃない?」となったんです。
──アコースティックバージョンにするにあたって、どんな作業が行われるのでしょうか?

藤原”34才”広明:曲によってですけれど、今回はジャムっぽい感じで、楽器隊で合わせていって、「あ、今の面白かったかも」と思ったものを土台として作っていきました。やっていることは再アレンジみたいなものなので、一応アイデアは持っていくんですけれど、その場で出たアイデアを試していくことで、面白さや意味を見つけられたらな、と僕は勝手に思っていて。だからみんなで楽しくワイワイやっていったら、面白い方に向かっていった、という感じではありました。
リーダー(上杉)が広げたフレーズに、もともと原曲の方で使っていたフレーズをちょっと分解したり。そういうのをいろいろ当てたり試したりしていたら、リーダーと合うところが出てきたので、「これはいいんじゃないか」みたいになっていたので、やなぎが「それならギターはこういうのはどう?」とかやっていったり。そういうやり取りをして、いろいろ広げていったんです。
──アコースティックバージョンは原曲の背中を強く押す感じとは違って、寄り添う形になっていますね。
渋谷龍太:アコースティックアレンジするなら、アコースティック然としていた方がいいと思っています。原曲からただテンポを落としたとか、ただそれっぽく聴こえるようにするのはあまり面白くないし、アレンジではないと思っているので。
おそらく1曲に対してのアプローチは正解が一つだけじゃないと思うんです。これぐらい見える景色を変えてくれると、他のとこから引っ張ってきたものであったりを、入れ込むだけの、また別の器になった感じがするから、同じものを入れようとはあまり思わなかったですね。
実はそんなにテンポ感が変わってないのと、言葉数がすごく多いから、一小節に何文字入ってるのっていうぐらい、入っているんです。実際、7文字とか入ってるから(笑)。それをあのテンポ感、あの空気感の中だと、歌う側はもちろんなんですけれど、耳で聴いた時に、一人だけ早歩きしているみたいな印象になりやすいんです。それはどうしても避けたくて、そこに対してのアプローチは、ちょっと大変でした。
SUPER BEAVERの曲は言葉一つに対して音符が1個ではなく、言葉一つの中に、音符が2個あったりするんですね。それがすごく多いから、純粋に音を変えなきゃいけない部分が、この曲はものすごく多いんですよ。それを勢いがある曲なら、パーっとやっても必死さ、一生懸命さというのがエッセンスになったりするんですけれど、ある程度、余裕を持ってやっている時に、そういう歌はちょっと違うんですよね。だからその部分の置き方みたいなところというのは、ちょっと苦労しますね。同じに歌ってしまうとダメなので。
ヒップホップみたいに、言葉を羅列するだけなら、たぶん一小節の中に8文字あったとしても、意外といけると思うんですよ。でもそこに節がついて、一つの言葉の中に音符が2つとかあったりすると、“あ、忙しいな”と耳で感じてしまうので。そのストレスを減らすために、どうしたらいいかというのは、結構やりましたね。もちろん聴いている人が“これは大変だったんだろうな”と思わせてしまったら本末転倒だから、なるたけ自然にして。
──アコースティックライブでは、そういう調整はたくさん必要になるのでしょうか?

渋谷龍太:意図としてやらなくてはいけないところは、実はそんなに多くないんです。そのまま歌って一番気持ちいいものが正解だと思うので。節とか変えたりするんですけど、計算して変えなくてはいけない部分は実はそんなに多くない。ただ『秘密』に関しては、最初にやってみた時に“お!”となりました。このままじゃ全然だめだ、と。
──ライブ「アコースティックのラクダ」はCOTTON CLUB、Billboard Libe OSAKAで行われる予定で、1月22日のNHKホール公演は、YouTubeで生配信もされるそうですね。
渋谷龍太:すごく聴きたいと言ってくださる方もたくさんいたし、自分たちも新たな試みだし、なるたけたくさんの方に聴いてほしいな、という気持ちが多かったので。YouTubeでの配信は、スマホやパソコンで開いて、アクセスすれば見ることができるので、たぶんこの時代では受け手にとって最も手間というハードルが低いから。聴いてもらいやすい環境でやるには何をやったらいいか、というところからですね。
明らかに現場に勝るものはない、というのはもちろん大前提だし、お金を取るということに恥じない活動をしてると思っているので。僕らにとっては、決して無料にすることが正ではないんですよ。ただ広く聴いていただいたり、楽しんでもらいたいと思うからこその、ひとつの方法ですね。
これを見て「実際に会場で聴きたかった」となったら、時間とお金を作ってもらって見に来てもらうべきだと僕は思ってるから。ただたくさん応募あったし、みんなこのご時世、大変な思いをしているだろうから、日頃の感謝を込めて、こういった機会を作りましたので、楽しんでもらいたいです。

TEXTキャベトンコ
PHOTO Kei Sakuhara
SUPER BEAVER(スーパービーバー)。 渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(G)、上杉研太(B)、藤原“35才”広明(Dr)の4人によって2005年に東京で結成された。 2009年6月にEPICレコードジャパンよりシングル「深呼吸」でメジャーデビュー。 2011年に活動の場をメジャーからインディーズへと移し、···