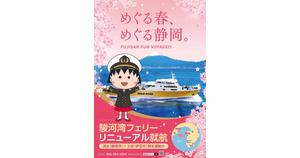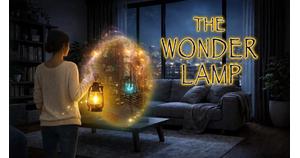ユダヤから世界に浸透した大ヒット曲

日本の童謡の中には、海外で生まれた歌を訳詞したり、アレンジを加えたりしたことで全国的に親しまれるようになった楽曲が存在します。
『ドナドナ』もそのひとつです。
『ドナドナ』は、1940年のイディッシュ語(ユダヤ人言語)ミュージカル「Esterke(エスターケ/エスターク/エステルク/エステルケ)」の劇中歌『Dana Dana(ダナダナ)』を原曲としています。
1961年に女性歌手のジョーン・バエズのカバーによりフォークソング『Dona Dona(ドナドナ)』として世界的に大ヒットし、日本でも1964年に『ドンナ・ドンナ』のタイトルでリリース。
その後、1966年に安井かずみによる訳詞を、子ども向けに変更した楽曲『ドナドナ』がNHK「みんなのうた」で放送され、長年小中学校の音楽教科書にも掲載される、メジャーな童謡として浸透しました。
暗い雰囲気のあるメロディと歌詞に、子どもながらに物悲しさを覚えた方も多いのではないでしょうか。
1番の冒頭は、次の歌詞で始まります。
----------------
ある晴れた昼さがり
市場へ続く道
≪ドナドナ 歌詞より抜粋≫
----------------
「ある晴れた昼さがり」のフレーズは暖かな日差しを感じさせ、晴れた日の穏やかな情景が目に浮かんでくるでしょう。
そこには「市場へ続く道」が延びています。
これだけなら単なるのどかな景色ですが、ここから切ないストーリーが展開されていきます。
どのような内容なのか、歌詞の意味を考察していきましょう。
売られていく子牛とそれを見つめる者たち

----------------
荷馬車がゴトゴト
子牛を乗せて行く
かわいい子牛 売られてゆくよ
悲しそうな瞳で見ているよ
≪ドナドナ 歌詞より抜粋≫
----------------
市場へ続く道を「荷馬車がゴトゴト」と音を立てながら走っていきます。
そこに乗っているのは「子牛」です。
「かわいい子牛 売られてゆくよ」というフレーズから、その子牛が売られるために荷馬車に乗せられていることは誰の目にも明らかです。
冒頭に「市場を続く道」とあるのも、荷馬車の目的地が市場であることを明確にしています。
この楽曲は売られる子牛目線の歌詞とされていますが、そうだとすると「悲しそうな瞳で見ているよ」と言っているのは誰なのでしょうか。
情景を思い浮かべてみると、子牛の目線の先には牧場に残る親や仲間の牛たち、荷馬車を見送る農夫がいると解釈できます。
売られること自体は理解できなくても、彼らと引き離されることを悟った子牛は、悲しさや諦めなどの複雑な気持ちを抱えて、彼らを見つめているのでしょう。
そして残る側もどうすることもできず、子牛をただ見つめています。
その間にあるやるせない気持ちが伝わってきますね。
----------------
ドナドナドナドナ
子牛を乗せて
ドナドナドナドナ
荷馬車が揺れる
≪ドナドナ 歌詞より抜粋≫
----------------
「ドナ(またはダナ)」は、牛を追い立てるときのかけ声だといわれています。
その点をふまえると、子牛自身がまるで住み慣れた土地から追い立てられているように感じているとも取れるでしょう。
最後に「荷馬車が揺れる」とつけ加えることで、荷馬車の走る音や振動、遠のいていく景色がありありとイメージできるのではないでしょうか。
子牛と燕の対比から見えるもの

----------------
青い空 そよぐ風
燕が飛びかう
荷馬車が市場へ
子牛を乗せて行く
≪ドナドナ 歌詞より抜粋≫
----------------
2番の歌詞も、美しい自然の風景から始まります。
頭上には「青い空」が広がり、優しく「そよぐ風」を感じます。
空を見上げると「燕が飛びかう」のが見え、その楽しそうな様子は子牛が売られていく悲しい状況と対照的です。
----------------
もしも翼が あったならば
楽しい牧場に帰れるものを
≪ドナドナ 歌詞より抜粋≫
----------------
子牛は燕の姿を見て、「もしも翼が あったならば」と考えます。
思い出されるのは、牧場での楽しい日々です。
ほかの子牛と走り回って遊んだ思い出や、親牛に寄り添って眠った心地よい時間。
もしも燕のように翼があれば、すぐにでもあの楽しい牧場に帰りたいと思っています。
しかし、その考えは叶わない夢でしかありません。
自由への渇望と厳しい現実に抗えない無力感は、人間にも通じるものです。
原曲はユダヤ人の音楽家たちによって作られたため、ヨーロッパでのユダヤ人排除の歴史を暗示していると考えられています。
事実は不明なものの、それを裏づけるかのように、原曲は日本語版よりも拘束されている子牛と自由な燕との対比がよりはっきりと描かれていて、世の不条理さが色濃く出ています。
どちらにしても悲しくつらい情景を表現した楽曲ですが、その裏にはどうにもならない現実の中でも、強く生きていかなければならないという想いがあるのではないでしょうか。
ただ子ども向けの悲しい曲と見るのではなく、歌詞をじっくりと考えることで、年代に関係なく教訓を得ていきたいですね。
時代を経てこそ改めて聴きたい名曲
童謡『ドナドナ』は子牛が売られていく道中の様子を切り取った、切なさが心に残る楽曲です。日本語版の誕生から半世紀以上が経過した今では学校で歌われることもなくなってしまいましたが、命の儚さや現実の厳しさを学ぶ上で大切にしたい名曲です。
大人になってから聴くと、子どもの頃とは違う視点で歌詞の意味を捉えることができるので、ぜひそれぞれの立場で聴いてみてください。