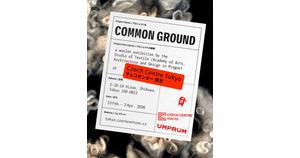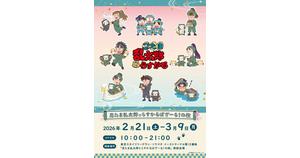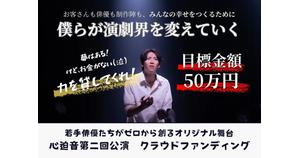2014年11月にはマリンメッセ福岡で1万人集めたライブを実施。集客力もあります。
C&Kがもつ「地元じゃなくても地元です」というスローガン。この精神をもって全国ツアーをまわる彼らは、日本人として歌を歌うことの意味をよく考えています。
「日本ビート」と名付けられたこの曲も日本の土着精神がこめらています。

「『異文化(まじわり)借りたら貸すのが理(ことわり) 借りすぎていた音楽
始まりだす さぁ 反撃の狼煙は純正 純 THE和」
というAメロの歌いだしがすでに挑戦的。「まじわり」と「ことわり」、そして「始まり」で韻をふんでいるうまさもあります。異文化、海外から借りてきた音楽をやるだけでなく、純粋な日本の音で勝負するぞという宣言。
まあ、細かいことを言い出すとそもそも西洋音階を使っているじゃないかとか、そういう話になるのですが、音階は西洋生まれでももっと日本流にアレンジしようよ、少なくとも日本語をもっと使ってみようよということをうったえたいのだと思います。
「123は一二三(ひふみ)」「Let' goはいくぞ」というフレーズも日本の土着精神のあらわれ。「すべては和の中にでもある」と歌うことに納得させられます。
そして出てくる
「風流なlyric 小粋なflow 祖先の血は絶やさせませぬ」のフレーズ。
リリックとかフローとか言ってるじゃないですか、純正の和じゃないですよ!というツッコミたくなってくるのです。
しかしこれは意図的にやっていること。そもそもタイトルの「ビート」も日本語だったら「拍子」です。ツッコミどころを残しつつも、それでもなお日本という土壌で勝負しようという意気込みの表れなのです。
あえて日本語と英語を混ぜている構成。ここに日本のポピュラー音楽の難しさが集約されています。
より激しいリズム、より複雑なリズムに日本語をのせるとどうしても無理が出てきてしまうのです。だからサザンのように早口で日本語をつめこんだり、ホルモンのように当て字を使ったり、エイベックスあたりでよくある日本語と英語を組み合わせたり、はたまた開き直って英語のみで歌う日本人アーティストが存在するのです。
C&Kは、曲に英語を混ぜつつも基本は日本語を使うタイプ。二人ともリズム感がとてつもなく良く、日本人離れしています。その二人が日本のビートについて歌うという皮肉も面白いですね。

TEXT:改訂木魚(じゃぶけん東京本部)